道交法改正とハンズフリー/コーデックキラー
アメニティ&サウンド 音と快適の空間へ vol.63
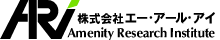
ARI CO.,LTD.
- Home >
- 音響と開発 >
- アメニティ&サウンド >
- バックナンバー >
- vol.63 道交法改正とハンズフリー/コーデックキラー

メールマガジン「アメニティ サウンド 音と快適の空間へ」は、現在、休刊中です。 バックナンバーのコラムの内、サウンドコラムと技術開発コラムは、 サウンド、技術開発コラム に再編集、一部加筆修正して掲載していますので併せてご利用ください。
■□■□■□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
■ アメニティ&サウンド 音と快適の空間へ【Vol.63】2004年11月4日
□ 道交法改正とハンズフリー/コーデックキラー
□ http://www.ari-web.com/
□■□□□□□□□□□□□□ 株式会社エー・アール・アイ □■□■
□…… CONTENTS Vol.63 ……………………………………………
■1.技術と開発の閑話 - 28 -
番外: F1とコンピュータ技術 - 後編 -
■2.サウンド - 60 -
デジタルアンプとデジタルスピーカ
-5- デジタルスピーカの特徴(1)
■3.3GPP音声通信 - 56 -
道交法改正とハンズフリー
ITU-T P.313音響規格 − 受話雑音測定
■4.コーデックキラー
(URLクリッピング)
………… はじめての方へ ………………………………………………
ご登録ありがとうございます。「アメニティ&サウンド 音と
快適の空間へ」は隔週(第1、第3木曜日)にお届けしています。
内容を充実できるように努力いたしますので末永くお付き合い
いただけますようお願い申し上げます。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1.技術と開発の閑話 - 28 -
番外: F1とコンピュータ技術 - 後編 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
技術や開発に関連した話題を閑話と題してお届けしています。あまり
専門的ではなく技術者以外の方にも接点のある内容にできればと考え
ています。
▼前回までの内容はバックナンバーをご覧ください。
http://www.ari-web.com/mm/
前回に続いてF1チームとコンピュータ技術の話題を続けます。
前回はF1車両のレギュレーション(規定)と技術に関してザッと書き
ました。(※前回触れていない技術のABSや排気量の変化、タイヤ、
燃料の規定など、コンピュータ技術関連以外にもスピードや安全性
に関してのレギュレーション変更は行われていることをここで少し
補足します。)
□……………………………………………………………………………
F1とIT技術
……………………………………………………………………□■□
F1の車体に関わるコンピュータ技術については、時々F1の雑誌など
で取り上げられるのですが、CNetの「ITが支えるF1世界最速技術」
という記事の後編に掲載されているようなデータベースやデータロ
ガー(テレメトリ)のデータの処理の話題はあまり見かけません。
マクラーレン・メルセデスは、記事にあるようにCA(コンピュータ・
アソシエイツ)社をパートナーにしています。ウィリアムズ・BMW
チームはHP社、フェラーリはAMDがスポンサー兼テクニカル・パー
トナーとなっています。
他のチームもそれぞれIT系の企業がスポンサーとしてだけでなく、
ITシステムのテクニカル・パートナーとなっています。
タイヤや自動車パーツ、機械部品や無線など各種のメーカーと提携
しカスタム・パーツを開発、生産する必要があるように、IT系も、
ソフトウェアを含めて技術的な開発が必要なため、IT企業の車体の
ロゴはパートナーとしてのマーキングでもあることが多いかと思い
ます(純粋なセールス・パートナーもあるので100%ではありません)。
プレスリリースなどで提携時に発表される「IT戦略システムで協業」
のような発言を聞くと、チームの公式サイトでも立ち上げ強力する
コマーシャル上の発表かと思ってしまいますが、テクニカル・パー
トナーとして参加している場合には、多少の差はあれCNetの記事に
あるようなITシステム面で協力しているのだと思います。
▼ITが支えるF1世界最速技術(前編)
CNET Japan 2004.9.27
http://japan.cnet.com/special/story/0,2000050158,20074778,00.htm
▼ITが支えるF1世界最速技術(後編)
CNET Japan 2004.10.04
http://japan.cnet.com/special/story/0,2000050158,20074920,00.htm
■耐久性まで品質管理
………………………………………………………………………□■□
記事に出ているマクラーレンというチームはトップチームであると
いうのみに留まらず、F1チームの中でも最も厳密なパーツ類の品質
管理を行っている1つと言われているチームです。
パーツは設計やテストにおいても厳密に計画され、レースに勝つた
めに必要な耐久度などにおいても製品の設計誤差が僅かになること
が求められているといわれています。
品質管理が厳密なだけに、F1中継で1台がトラブルで破損すると「
残る1台は大丈夫でしょうか」という発言に繋がっています。実際、
マクラーレンの2台がほぼ同じ周回数で類似したリタイアを見せた
ことが何回かあります。このようなシーンを見ると、設計やパーツ
製造上の問題においてバラツキが非常に少ないことが想像できます。
このような管理は市販製品でも行われていますが、毎年異なる車体
を設計し(しかもサーキットごとに少しづつ異なっている場合が普通
です)、外注部品まで含めて品質管理を行うような戦略性が必要とさ
れ、ITシステムにおいてもシビアな要求が行われているものと想像
できます(トラブルが発生するとロン・デニスはかなり怖そうです)。
■コンピュータシミュレーション
………………………………………………………………………□■□
コンピュータ・シミュレーションは、風洞実験などと合わせて開発
で行われているのとレース戦略(ピットストップなど)のシミュレー
ションが行われていることは、以前に何かで紹介されたものを見た
ことがありましたが、決勝中にもトランスポーターの中のサーバー
でシミュレーションを逐次行ってパドックのノートPCと通信してい
るというのはこの記事で初めて知りました。
現在のF1は、エンジンが良い、ドライバーが良い、空力に優れると
いうような1点のみでは勝てないといわれており、トップクラスの
チームは風洞設備やシミュレーションが必須とされています。
シミュレーションは当然コンピュータの出番ですが、テストの走行
データの管理や分析など、言われて見るともっともなITシステムの
活躍する場所があることに気付きます。
■増加するデータ量
………………………………………………………………………□■□
シミュレーション関係が増加しているのではないかとい想像します
が年々システムのデータ量が増加しているようです。
現在は、本番のレースは3日間1エンジンと決められているため、
サーキットでレース・ディスタンスの長距離走行テストを行うのは、
予備車の1台のみですし、共同テストもコストを削減する目的と、
ドライバーの休日を確保するために回数を圧縮してきています。
テスト走行は減少方向にあるわけですから、データの詳細度が向上
した代わりにテスト距離が減少して、それなりの増加量になるだけ
のように思いますが実際には相当増加しているようです(マクラー
レンは独自のテスト走行も相当行っていそうなので走行量が減って
いないかもしれませんが)。
CNetの記事には「2004年には8テラバイトまでに膨れ上がっている」
など、F1専門誌でもあまり見かけない内容がいくつも紹介されてい
ますので興味がある方はオススメです。
それでは、次回もよろしくお付き合いください。(^^)
----------------------------------------------------------
▼ARIはアプリケーションソフトやデジタル機器の開発などを
お手伝いしています。
http://www.ari-web.com/develop/index.htm
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■2.サウンド - 60 -
デジタルアンプとデジタルスピーカ -5-
デジタルスピーカの特徴(1)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
このコラムは音や音響機器などについての話題をお届けしています。
デジタルアンプとデジタルスピーカについての話題を続けます。
▼前回までの内容はバックナンバーをご覧ください。
http://www.ari-web.com/mm/
これまでデジタルアンプの特徴として次のような特徴について述べ
ました。これらの特徴から、さらに「省スペースで小型化できる」
という利点も生じます。
──────────────────────────
・効率が良く省電力
・発熱が少ない
・シンプルな構成
・経路での雑音が出力に影響しない(しにくい)
・クロスオーバ歪みが発生しない
──────────────────────────
デジタル・オーディオという言葉が使われるようになって久しいわ
けですが、アンプ、スピーカと中央部分から音を発するスピーカま
でアナログで記録メディアと一部の伝送経路のみデジタル化された
だけに近いものでしたが、デジタルアンプは、パワーアンプの時点
までをフルデジタルに変えます。
以前は、高速スイッチングすることによる雑音の問題を解決するこ
とが技術的に難しく、結果、D級アンプは音質もD級というような
印象が強かったわけですが、前回述べたように原理的な部分におい
てはクロスオーバー歪みや効率など利点が生かせるため、現在では
むしろ、ハイエンド製品ほどハイファイのデジタルアンプを目指す
というような動向になっているといえます。
□……………………………………………………………………………
デジタルスピーカ
……………………………………………………………………□■□
さて、ここでデジタルスピーカに視点を移します。
デジタルスピーカは、デジタルといってもスピーカの空気の振動に
変換する部分は同じです。スピーカ内部にデジタルアンプを内蔵し
ていてデジタル信号入力を受けるアクティブ・スピーカです。
デジタルスピーカの中にも、アンプはアナログのものもありますが
今後はデジタルアンプを内蔵しているものが一般的になるでしょう。
呼称も「デジタルスピーカ」と呼ばれたり「デジタルアンプ内蔵型
スピーカ」と呼ばれる場合などデジタルアンプに比較すると決定的
ではありません。従来のアクティブスピーカのポジションにある製
品がデジタルスピーカ化してゆくということは確かでしょうが、家
庭で利用する場合には電源をスピーカそれぞれで確保しなければい
けなくなりますから(あるいは専用のアンプから信号線と一緒に供給
するなど)、コンシューマ製品として、普及するかというと疑問では
あります。
家庭用の場合には、伝送路も短いですから耐ノイズ性やケーブルの
問題は深刻な問題ではありません。
デジタルスピーカのアンプ以外の利点としては
──────────────────────────
・伝送路での耐ノイズ性能が高い
・ケーブル敷設工事が簡単
・DSPなどで調整機能をスピーカで実現
・インテリジェント化可能
──────────────────────────
というメリットが考えられます。
耐ノイズ性能は特に述べるまでもないでしょう。ただし、エラー・
リカバリができないほどのデータ欠損が発生するような場合には、
他のデジタル機器、CDなどと同様、音声が完全に欠損する状態に
もなります。
商業施設などにおいては、長距離の伝送路にケーブルを敷設する必
要が生じるためケーブルがシンプルになることなど大きな利点とも
なります。配管やケーブル本数、サイズ、重量などデジタルにする
ことで音質以外のケーブルというファクターで大きなメリットが存
在します。
この場合も電源は必要になりますから、設備の性質によるというこ
とになりますが……
次回はデジタルスピーカの特徴について続けたいと思います。
それでは、次回もよろしくお付き合いください。(^^)
----------------------------------------------------------
▼ARIは音響機器の開発や電気音響システムの設計、測定をお手伝
いしています。
http://www.ari-web.com/develop/index.htm
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■3.3GPP音声通信(56)
ITU-T P.313音響規格 − 受話雑音測定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
ご存知のように11月1日の道路交通法改正で自動車運転中の携帯電話
使用に対する罰則が強化されましたが、初日が3645件、11/3日まで
に6000件以上の違反取締りを行ったようです。
■道交法改正とハンズフリー
………………………………………………………………………□■□
今回の改正前までは「交通の危険を生じさせた場合に限って、3月
以下の懲役又は5万円以下の罰金」となっていましたが今回の改正
では次のように「手に保持して」で違反となります。
・無線通話装置を手で保持して通話のために使用すること
・画像表示用装置を手で保持して表示された画像を注視すること
▼警察庁
http://www.npa.go.jp/
▼改正道交法Q&Aのページ
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20/KaiseiQ_A.htm
一般に携帯電話の通話とメールなどを指すと紹介されますが、当然
ながら携帯電話以外の無線、PDA、ゲーム、PC、携帯TV等も
「手に保持して画像を注視」すると違反となるでしょう。
道路交通法では「手に保持して」と手操作を伴うものを禁止してい
ますから、ハンズフリー装置を併用してヘッドセット通話している
場合には「手に保持」はしていないため違反とはなりません。
しかしながら、各都道府県の公安委員会で禁止されている場合には
違反となるという遵守事項の違反となります。今のところ片耳タイ
プのヘッドセットだと違反にはならないという記事がありますが…
▼運転時のヘッドセット着用、各県でおおむね利用に問題なし
インプレス ケータイWatch
http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/21185.html
東京都のようにイヤホンでラジオを聞いている場合も安全性に問題
があるとみなされれば違反となる場合もあります。上の記事中でも
触れられていますが、イヤホンの中には補聴器もあるためイヤホン
やヘッドホン(これはダメかも)のみで違反とするものではありませ
ん。
ハンズフリー通話に関しては、業務上、無線通話が必要な人がいる
ため、海外などでも例外とする考え方が主流のようですが、日本に
限らず、米国などでも携帯電話通話中の事故件数を問題にしていま
すから、法令違反ではないにしても統計的に事故につながりやすい
ことは確かでしょう。
渋滞時に連絡したくなったり、電子メールの確認などをしたいこと
は多いかと思いますが、「手に保持して」は道交法違反となるため
危険性が低くても「法の厳守」という考え方で取り締まり対象とな
るかもしれません(危険に繋がった場合では無くなったので)。
自動車での移動時に連絡が必要になることが多い方はハンズフリー
装置が必要かもしれません。
□……………………………………………………………………………
■9.Receiving Idle channel noise
(受話雑音)
………………………………………………………………………□■□
さて、前回はITU-T P.313規格の送話雑音測定についてでした。
今回は受話雑音測定についてです。
▼前回までの内容はバックナンバーをご覧ください。
http://www.ari-web.com/mm/
ITU-T P313規格とはPDC方式の携帯端末の音響性能を評価する上で
望ましい測定項目が揃っている音響規格です。
▼ITU-T規格については以前にご紹介しました。
http://www.ari-web.com/mm/bn/20030515.htm
受話雑音測定とは、受話方向の測定で端末が通話状態で無信号時の
雑音レベルを評価するための測定です。つまり、相手の端末とつな
がっていて話をしていない状態で受話器からどの程度雑音が聞こえ
ているかを評価するということです。
受話時の雑音とは送話端末(POI点)から受話端末の受話器(ERP点)
までの全てのノイズの事を指しており、人工耳マイクに入力される
周囲雑音のノイズや端末自体の回路のノイズ、伝送経路のノイズな
ど受話経路の全てのノイズを含みます。
測定にはLRGP(テストヘッド)を使用します。測定環境については
周囲環境が30dBspl(A)以下の環境で測定する様に規定されています。
測定は無信号時の雑音レベルを評価するので試験信号は使用しませ
ん。これらの測定条件は3GPP規格の受話雑音測定と同じです。
▼3GPP規格の受話雑音測定は以前にご紹介しました。
http://www.ari-web.com/mm/bn/20021205.htm
測定方法は端末を通話状態にし、受話器から出力される音声の周波
数分布、レベルを人工耳マイク(ERP点)で測定し、全周波帯域の
総和レベルを求めます。この求めた総和レベルが受話雑音レベルと
いうことになります。また、ERP点にはA特性の周波数重み付けをし
て測定を行います。
▼A特性周波数重み付けについては以前にご紹介しました。
http://www.ari-web.com/mm/bn/20031120.htm
規格では受話雑音は以下の値で規定されています。
・受話雑音レベル :-56dBPa(A)以下
(周囲雑音30dBspl(A)以下のにて)
受話雑音レベルが大きすぎると相手の声が聞き取りにくくなったり、
雑音の周波数成分によっては受話音声をマスキングするなどど通話
品質に著しく影響するので、受話雑音レベルは十分に抑えられてい
る必要があります。
次回は送話利得測定についてお届けしたいと思います。
----------------------------------------------------------
▼ARIは3GPP,GSM,PDC音響測定に対応した「3G携帯通信開発用
音響測定システム MTA-01WB-S」を開発・販売しています。
http://www.ari-web.com/mobile/3g/mta01-wbs/info-3gpp.htm
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■4.コーデックキラー
(URLクリッピング)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
WEB参照可能な掲載記事などから毎日伝えられるニュースや記事か
ら気になる情報や翌日には埋もれてしまいそうな記事をピックアッ
プしてご紹介しています(このメールマガジンの発行周期が隔週と
いうこともあって新しい記事ばかりではありません)。
□……………………………………………………………………………
■コーデックキラー
………………………………………………………………………□■□
先月「コーデックキラー」という言葉をはじめて知りました。
音楽をエンコードした時、何らかの音声品質が劣る部分が出来てし
まうタイプの音源のことをコーデックキラーと呼ぶようです。
▼オンライン音楽サービスの前に立ちはだかる
「コーデックキラー」問題
CNet Japan News ネットとメディア 2004/10/25
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000047715,20075354,00.htm
コーデック(CODEC)というのは圧縮/復元(COmpress/DECompress)
するものやコード変換/復元(COrder/DEcorder)するソフトウェアや
装置のことです。
音楽配信で使われているmp3やMDなどのデジタル音楽データは圧縮
してサイズを軽減するため聴感上原音との差異が少なくなるような
冗長な部分を間引きしてデータ変換されています。
通常、マスキング(他の音で良く聞き取れない信号)される周波数帯
域を間引くことでデータを単純化しているような処理がなされます。
コーデックキラーはこの圧縮処理を行うと不正なノイズや音と認識
されるようなデータになってしまう音源を指しています。
「オンライン音楽サービスの前に立ちはだかる……」という表現が
されていますので全くコード化できないということかと勘違いしそ
うですが、音質に問題があるため商品性の問題として「前に立ちは
だかる……」ということのようです。
映像を考えてみると、DVDや地上デジタルなどの圧縮された映像に
はブロックノイズやモスキートノイズなどの劣化が見られる場合も
珍しくはありませんが、ブロックノイズが出やすくなる音楽コンサ
ートのソフトなどを「コーデックキラー」とまでは言わないと思い
ます。
聴覚は視覚に比べると非常にシビアであることは確かですが、全て
の人が音楽では劣化が全く許されないということも無いでしょうか
ら、コストパフォーマンスなどサービスの種類によるのでしょうね。
具体的なコーデックキラーは紹介されていないので、どのようにし
て「プレエコー」などの問題が発生しているか、どの程度の劣化に
なっているのかが解りませんが、仮に音質が良いという点をセール
スにしているような配信をする場合には深刻な問題となるかもしれ
ません。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
■編集後記
F1のコンピュータ技術の話題などに注目する割にはARIは車載関連
はやっていません……CQ出版の「組込みネット」によると「車載
やっています」というのがトレンドらしいので、トレンドから少し
はずれていますね。
2回に詰め込んだのでやや舌足らずな感じになっていますがレース
のコラムではないので2回程度が相応ではないかと考えています。
最近のF1はオーバーテイク(追い抜き)も少なく運転するドライバー
最近、メディアによってはドライバーと呼ばず、F1パイロットと呼
ばれている場合があります。「運転」ではなく「操縦」だという意
図でしょうか?
ドライビングという言葉は使われているので個人的には中途半端で
はないかという気がします。ステアリングは自動車のハンドルとい
うより操縦桿のような面持ちになっていますし、電子制御でフライ
バイワイヤーという航空機の言葉も使っていますから、パイロット
的だということなのかもしれません。
それでは、次回2004年11月18日Vol.64もよろしくお願いします。
ARI A&S 編集部
【配信】…………………………………………………………………□■□
このメールマガジンは、次のメール配信サービスによって発行
されています。
Melma! : http://www.melma.com/
まぐまぐ: http://www.mag2.com/
Macky!: http://macky.nifty.com/
めろんぱん: http://www.melonpan.net
メルマガ天国:http://melten.com/
E-Magazine: http://www.emaga.com/
カプライト: http://kapu.biglobe.ne.jp/
【配信中止】……………………………………………………………□■□
配信中止をご希望の方がいらっしゃいましたら、お手数ですが、
登録いただいた各配信先で解除いただきますようお願い申し上げ
ます。(みなさまにご登録いただいたメールアドレスは弊社では
記録、収集しておりません)。
Melma! http://www.melma.com/mag/96/m00058796/index_bn.html
まぐまぐ http://www.mag2.com/m/0000086886.htm
Macky! http://macky.nifty.com/cgi-bin/bndisp.cgi?M-ID=poparimm
めろんぱん http://www.melonpan.net/melonpa/mag-detail.php?mag_id=002937
メルマガ天国 http://melten.com/m/10326.html
E-Magazine http://www.emaga.com/info/arimm.html
カプライト http://cgi.kapu.biglobe.ne.jp/m/5842.html
【ご意見・ご感想】……………………………………………………□■□
このメールマガジンが対象としているような技術や音響などの
内容についてご意見、ご感想、投稿など歓迎いたしますので、
なんでもお気軽にお寄せください。
▼ご意見、ご感想送信はこちらのE-Mailアドレスへお願いします。
mailto:news@ari-web.com
□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□ 発行/編集 株式会社エー・アール・アイ
□ Amenity Research Institute Co.,Ltd.
□ 〒192-0081 東京都八王子市横山町6-9 丸多屋ビル8F
□ TEL :0426-56-2771 FAX :0426-56-2654
□ URL : http://www.ari-web.com/
■ お問合せ : mailto:news@ari-web.com
■ Copyright(C) 2004. ARI.CO.,LTD. All Rights Reserved.
□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□■□■□■
■ アメニティ&サウンド 音と快適の空間へ【Vol.63】2004年11月4日
□ 道交法改正とハンズフリー/コーデックキラー
□ http://www.ari-web.com/
□■□□□□□□□□□□□□ 株式会社エー・アール・アイ □■□■
□…… CONTENTS Vol.63 ……………………………………………
■1.技術と開発の閑話 - 28 -
番外: F1とコンピュータ技術 - 後編 -
■2.サウンド - 60 -
デジタルアンプとデジタルスピーカ
-5- デジタルスピーカの特徴(1)
■3.3GPP音声通信 - 56 -
道交法改正とハンズフリー
ITU-T P.313音響規格 − 受話雑音測定
■4.コーデックキラー
(URLクリッピング)
………… はじめての方へ ………………………………………………
ご登録ありがとうございます。「アメニティ&サウンド 音と
快適の空間へ」は隔週(第1、第3木曜日)にお届けしています。
内容を充実できるように努力いたしますので末永くお付き合い
いただけますようお願い申し上げます。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1.技術と開発の閑話 - 28 -
番外: F1とコンピュータ技術 - 後編 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
技術や開発に関連した話題を閑話と題してお届けしています。あまり
専門的ではなく技術者以外の方にも接点のある内容にできればと考え
ています。
▼前回までの内容はバックナンバーをご覧ください。
http://www.ari-web.com/mm/
前回に続いてF1チームとコンピュータ技術の話題を続けます。
前回はF1車両のレギュレーション(規定)と技術に関してザッと書き
ました。(※前回触れていない技術のABSや排気量の変化、タイヤ、
燃料の規定など、コンピュータ技術関連以外にもスピードや安全性
に関してのレギュレーション変更は行われていることをここで少し
補足します。)
□……………………………………………………………………………
F1とIT技術
……………………………………………………………………□■□
F1の車体に関わるコンピュータ技術については、時々F1の雑誌など
で取り上げられるのですが、CNetの「ITが支えるF1世界最速技術」
という記事の後編に掲載されているようなデータベースやデータロ
ガー(テレメトリ)のデータの処理の話題はあまり見かけません。
マクラーレン・メルセデスは、記事にあるようにCA(コンピュータ・
アソシエイツ)社をパートナーにしています。ウィリアムズ・BMW
チームはHP社、フェラーリはAMDがスポンサー兼テクニカル・パー
トナーとなっています。
他のチームもそれぞれIT系の企業がスポンサーとしてだけでなく、
ITシステムのテクニカル・パートナーとなっています。
タイヤや自動車パーツ、機械部品や無線など各種のメーカーと提携
しカスタム・パーツを開発、生産する必要があるように、IT系も、
ソフトウェアを含めて技術的な開発が必要なため、IT企業の車体の
ロゴはパートナーとしてのマーキングでもあることが多いかと思い
ます(純粋なセールス・パートナーもあるので100%ではありません)。
プレスリリースなどで提携時に発表される「IT戦略システムで協業」
のような発言を聞くと、チームの公式サイトでも立ち上げ強力する
コマーシャル上の発表かと思ってしまいますが、テクニカル・パー
トナーとして参加している場合には、多少の差はあれCNetの記事に
あるようなITシステム面で協力しているのだと思います。
▼ITが支えるF1世界最速技術(前編)
CNET Japan 2004.9.27
http://japan.cnet.com/special/story/0,2000050158,20074778,00.htm
▼ITが支えるF1世界最速技術(後編)
CNET Japan 2004.10.04
http://japan.cnet.com/special/story/0,2000050158,20074920,00.htm
■耐久性まで品質管理
………………………………………………………………………□■□
記事に出ているマクラーレンというチームはトップチームであると
いうのみに留まらず、F1チームの中でも最も厳密なパーツ類の品質
管理を行っている1つと言われているチームです。
パーツは設計やテストにおいても厳密に計画され、レースに勝つた
めに必要な耐久度などにおいても製品の設計誤差が僅かになること
が求められているといわれています。
品質管理が厳密なだけに、F1中継で1台がトラブルで破損すると「
残る1台は大丈夫でしょうか」という発言に繋がっています。実際、
マクラーレンの2台がほぼ同じ周回数で類似したリタイアを見せた
ことが何回かあります。このようなシーンを見ると、設計やパーツ
製造上の問題においてバラツキが非常に少ないことが想像できます。
このような管理は市販製品でも行われていますが、毎年異なる車体
を設計し(しかもサーキットごとに少しづつ異なっている場合が普通
です)、外注部品まで含めて品質管理を行うような戦略性が必要とさ
れ、ITシステムにおいてもシビアな要求が行われているものと想像
できます(トラブルが発生するとロン・デニスはかなり怖そうです)。
■コンピュータシミュレーション
………………………………………………………………………□■□
コンピュータ・シミュレーションは、風洞実験などと合わせて開発
で行われているのとレース戦略(ピットストップなど)のシミュレー
ションが行われていることは、以前に何かで紹介されたものを見た
ことがありましたが、決勝中にもトランスポーターの中のサーバー
でシミュレーションを逐次行ってパドックのノートPCと通信してい
るというのはこの記事で初めて知りました。
現在のF1は、エンジンが良い、ドライバーが良い、空力に優れると
いうような1点のみでは勝てないといわれており、トップクラスの
チームは風洞設備やシミュレーションが必須とされています。
シミュレーションは当然コンピュータの出番ですが、テストの走行
データの管理や分析など、言われて見るともっともなITシステムの
活躍する場所があることに気付きます。
■増加するデータ量
………………………………………………………………………□■□
シミュレーション関係が増加しているのではないかとい想像します
が年々システムのデータ量が増加しているようです。
現在は、本番のレースは3日間1エンジンと決められているため、
サーキットでレース・ディスタンスの長距離走行テストを行うのは、
予備車の1台のみですし、共同テストもコストを削減する目的と、
ドライバーの休日を確保するために回数を圧縮してきています。
テスト走行は減少方向にあるわけですから、データの詳細度が向上
した代わりにテスト距離が減少して、それなりの増加量になるだけ
のように思いますが実際には相当増加しているようです(マクラー
レンは独自のテスト走行も相当行っていそうなので走行量が減って
いないかもしれませんが)。
CNetの記事には「2004年には8テラバイトまでに膨れ上がっている」
など、F1専門誌でもあまり見かけない内容がいくつも紹介されてい
ますので興味がある方はオススメです。
それでは、次回もよろしくお付き合いください。(^^)
----------------------------------------------------------
▼ARIはアプリケーションソフトやデジタル機器の開発などを
お手伝いしています。
http://www.ari-web.com/develop/index.htm
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■2.サウンド - 60 -
デジタルアンプとデジタルスピーカ -5-
デジタルスピーカの特徴(1)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
このコラムは音や音響機器などについての話題をお届けしています。
デジタルアンプとデジタルスピーカについての話題を続けます。
▼前回までの内容はバックナンバーをご覧ください。
http://www.ari-web.com/mm/
これまでデジタルアンプの特徴として次のような特徴について述べ
ました。これらの特徴から、さらに「省スペースで小型化できる」
という利点も生じます。
──────────────────────────
・効率が良く省電力
・発熱が少ない
・シンプルな構成
・経路での雑音が出力に影響しない(しにくい)
・クロスオーバ歪みが発生しない
──────────────────────────
デジタル・オーディオという言葉が使われるようになって久しいわ
けですが、アンプ、スピーカと中央部分から音を発するスピーカま
でアナログで記録メディアと一部の伝送経路のみデジタル化された
だけに近いものでしたが、デジタルアンプは、パワーアンプの時点
までをフルデジタルに変えます。
以前は、高速スイッチングすることによる雑音の問題を解決するこ
とが技術的に難しく、結果、D級アンプは音質もD級というような
印象が強かったわけですが、前回述べたように原理的な部分におい
てはクロスオーバー歪みや効率など利点が生かせるため、現在では
むしろ、ハイエンド製品ほどハイファイのデジタルアンプを目指す
というような動向になっているといえます。
□……………………………………………………………………………
デジタルスピーカ
……………………………………………………………………□■□
さて、ここでデジタルスピーカに視点を移します。
デジタルスピーカは、デジタルといってもスピーカの空気の振動に
変換する部分は同じです。スピーカ内部にデジタルアンプを内蔵し
ていてデジタル信号入力を受けるアクティブ・スピーカです。
デジタルスピーカの中にも、アンプはアナログのものもありますが
今後はデジタルアンプを内蔵しているものが一般的になるでしょう。
呼称も「デジタルスピーカ」と呼ばれたり「デジタルアンプ内蔵型
スピーカ」と呼ばれる場合などデジタルアンプに比較すると決定的
ではありません。従来のアクティブスピーカのポジションにある製
品がデジタルスピーカ化してゆくということは確かでしょうが、家
庭で利用する場合には電源をスピーカそれぞれで確保しなければい
けなくなりますから(あるいは専用のアンプから信号線と一緒に供給
するなど)、コンシューマ製品として、普及するかというと疑問では
あります。
家庭用の場合には、伝送路も短いですから耐ノイズ性やケーブルの
問題は深刻な問題ではありません。
デジタルスピーカのアンプ以外の利点としては
──────────────────────────
・伝送路での耐ノイズ性能が高い
・ケーブル敷設工事が簡単
・DSPなどで調整機能をスピーカで実現
・インテリジェント化可能
──────────────────────────
というメリットが考えられます。
耐ノイズ性能は特に述べるまでもないでしょう。ただし、エラー・
リカバリができないほどのデータ欠損が発生するような場合には、
他のデジタル機器、CDなどと同様、音声が完全に欠損する状態に
もなります。
商業施設などにおいては、長距離の伝送路にケーブルを敷設する必
要が生じるためケーブルがシンプルになることなど大きな利点とも
なります。配管やケーブル本数、サイズ、重量などデジタルにする
ことで音質以外のケーブルというファクターで大きなメリットが存
在します。
この場合も電源は必要になりますから、設備の性質によるというこ
とになりますが……
次回はデジタルスピーカの特徴について続けたいと思います。
それでは、次回もよろしくお付き合いください。(^^)
----------------------------------------------------------
▼ARIは音響機器の開発や電気音響システムの設計、測定をお手伝
いしています。
http://www.ari-web.com/develop/index.htm
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■3.3GPP音声通信(56)
ITU-T P.313音響規格 − 受話雑音測定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
ご存知のように11月1日の道路交通法改正で自動車運転中の携帯電話
使用に対する罰則が強化されましたが、初日が3645件、11/3日まで
に6000件以上の違反取締りを行ったようです。
■道交法改正とハンズフリー
………………………………………………………………………□■□
今回の改正前までは「交通の危険を生じさせた場合に限って、3月
以下の懲役又は5万円以下の罰金」となっていましたが今回の改正
では次のように「手に保持して」で違反となります。
・無線通話装置を手で保持して通話のために使用すること
・画像表示用装置を手で保持して表示された画像を注視すること
▼警察庁
http://www.npa.go.jp/
▼改正道交法Q&Aのページ
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20/KaiseiQ_A.htm
一般に携帯電話の通話とメールなどを指すと紹介されますが、当然
ながら携帯電話以外の無線、PDA、ゲーム、PC、携帯TV等も
「手に保持して画像を注視」すると違反となるでしょう。
道路交通法では「手に保持して」と手操作を伴うものを禁止してい
ますから、ハンズフリー装置を併用してヘッドセット通話している
場合には「手に保持」はしていないため違反とはなりません。
しかしながら、各都道府県の公安委員会で禁止されている場合には
違反となるという遵守事項の違反となります。今のところ片耳タイ
プのヘッドセットだと違反にはならないという記事がありますが…
▼運転時のヘッドセット着用、各県でおおむね利用に問題なし
インプレス ケータイWatch
http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/21185.html
東京都のようにイヤホンでラジオを聞いている場合も安全性に問題
があるとみなされれば違反となる場合もあります。上の記事中でも
触れられていますが、イヤホンの中には補聴器もあるためイヤホン
やヘッドホン(これはダメかも)のみで違反とするものではありませ
ん。
ハンズフリー通話に関しては、業務上、無線通話が必要な人がいる
ため、海外などでも例外とする考え方が主流のようですが、日本に
限らず、米国などでも携帯電話通話中の事故件数を問題にしていま
すから、法令違反ではないにしても統計的に事故につながりやすい
ことは確かでしょう。
渋滞時に連絡したくなったり、電子メールの確認などをしたいこと
は多いかと思いますが、「手に保持して」は道交法違反となるため
危険性が低くても「法の厳守」という考え方で取り締まり対象とな
るかもしれません(危険に繋がった場合では無くなったので)。
自動車での移動時に連絡が必要になることが多い方はハンズフリー
装置が必要かもしれません。
□……………………………………………………………………………
■9.Receiving Idle channel noise
(受話雑音)
………………………………………………………………………□■□
さて、前回はITU-T P.313規格の送話雑音測定についてでした。
今回は受話雑音測定についてです。
▼前回までの内容はバックナンバーをご覧ください。
http://www.ari-web.com/mm/
ITU-T P313規格とはPDC方式の携帯端末の音響性能を評価する上で
望ましい測定項目が揃っている音響規格です。
▼ITU-T規格については以前にご紹介しました。
http://www.ari-web.com/mm/bn/20030515.htm
受話雑音測定とは、受話方向の測定で端末が通話状態で無信号時の
雑音レベルを評価するための測定です。つまり、相手の端末とつな
がっていて話をしていない状態で受話器からどの程度雑音が聞こえ
ているかを評価するということです。
受話時の雑音とは送話端末(POI点)から受話端末の受話器(ERP点)
までの全てのノイズの事を指しており、人工耳マイクに入力される
周囲雑音のノイズや端末自体の回路のノイズ、伝送経路のノイズな
ど受話経路の全てのノイズを含みます。
測定にはLRGP(テストヘッド)を使用します。測定環境については
周囲環境が30dBspl(A)以下の環境で測定する様に規定されています。
測定は無信号時の雑音レベルを評価するので試験信号は使用しませ
ん。これらの測定条件は3GPP規格の受話雑音測定と同じです。
▼3GPP規格の受話雑音測定は以前にご紹介しました。
http://www.ari-web.com/mm/bn/20021205.htm
測定方法は端末を通話状態にし、受話器から出力される音声の周波
数分布、レベルを人工耳マイク(ERP点)で測定し、全周波帯域の
総和レベルを求めます。この求めた総和レベルが受話雑音レベルと
いうことになります。また、ERP点にはA特性の周波数重み付けをし
て測定を行います。
▼A特性周波数重み付けについては以前にご紹介しました。
http://www.ari-web.com/mm/bn/20031120.htm
規格では受話雑音は以下の値で規定されています。
・受話雑音レベル :-56dBPa(A)以下
(周囲雑音30dBspl(A)以下のにて)
受話雑音レベルが大きすぎると相手の声が聞き取りにくくなったり、
雑音の周波数成分によっては受話音声をマスキングするなどど通話
品質に著しく影響するので、受話雑音レベルは十分に抑えられてい
る必要があります。
次回は送話利得測定についてお届けしたいと思います。
----------------------------------------------------------
▼ARIは3GPP,GSM,PDC音響測定に対応した「3G携帯通信開発用
音響測定システム MTA-01WB-S」を開発・販売しています。
http://www.ari-web.com/mobile/3g/mta01-wbs/info-3gpp.htm
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■4.コーデックキラー
(URLクリッピング)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
WEB参照可能な掲載記事などから毎日伝えられるニュースや記事か
ら気になる情報や翌日には埋もれてしまいそうな記事をピックアッ
プしてご紹介しています(このメールマガジンの発行周期が隔週と
いうこともあって新しい記事ばかりではありません)。
□……………………………………………………………………………
■コーデックキラー
………………………………………………………………………□■□
先月「コーデックキラー」という言葉をはじめて知りました。
音楽をエンコードした時、何らかの音声品質が劣る部分が出来てし
まうタイプの音源のことをコーデックキラーと呼ぶようです。
▼オンライン音楽サービスの前に立ちはだかる
「コーデックキラー」問題
CNet Japan News ネットとメディア 2004/10/25
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000047715,20075354,00.htm
コーデック(CODEC)というのは圧縮/復元(COmpress/DECompress)
するものやコード変換/復元(COrder/DEcorder)するソフトウェアや
装置のことです。
音楽配信で使われているmp3やMDなどのデジタル音楽データは圧縮
してサイズを軽減するため聴感上原音との差異が少なくなるような
冗長な部分を間引きしてデータ変換されています。
通常、マスキング(他の音で良く聞き取れない信号)される周波数帯
域を間引くことでデータを単純化しているような処理がなされます。
コーデックキラーはこの圧縮処理を行うと不正なノイズや音と認識
されるようなデータになってしまう音源を指しています。
「オンライン音楽サービスの前に立ちはだかる……」という表現が
されていますので全くコード化できないということかと勘違いしそ
うですが、音質に問題があるため商品性の問題として「前に立ちは
だかる……」ということのようです。
映像を考えてみると、DVDや地上デジタルなどの圧縮された映像に
はブロックノイズやモスキートノイズなどの劣化が見られる場合も
珍しくはありませんが、ブロックノイズが出やすくなる音楽コンサ
ートのソフトなどを「コーデックキラー」とまでは言わないと思い
ます。
聴覚は視覚に比べると非常にシビアであることは確かですが、全て
の人が音楽では劣化が全く許されないということも無いでしょうか
ら、コストパフォーマンスなどサービスの種類によるのでしょうね。
具体的なコーデックキラーは紹介されていないので、どのようにし
て「プレエコー」などの問題が発生しているか、どの程度の劣化に
なっているのかが解りませんが、仮に音質が良いという点をセール
スにしているような配信をする場合には深刻な問題となるかもしれ
ません。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
■編集後記
F1のコンピュータ技術の話題などに注目する割にはARIは車載関連
はやっていません……CQ出版の「組込みネット」によると「車載
やっています」というのがトレンドらしいので、トレンドから少し
はずれていますね。
2回に詰め込んだのでやや舌足らずな感じになっていますがレース
のコラムではないので2回程度が相応ではないかと考えています。
最近のF1はオーバーテイク(追い抜き)も少なく運転するドライバー
最近、メディアによってはドライバーと呼ばず、F1パイロットと呼
ばれている場合があります。「運転」ではなく「操縦」だという意
図でしょうか?
ドライビングという言葉は使われているので個人的には中途半端で
はないかという気がします。ステアリングは自動車のハンドルとい
うより操縦桿のような面持ちになっていますし、電子制御でフライ
バイワイヤーという航空機の言葉も使っていますから、パイロット
的だということなのかもしれません。
それでは、次回2004年11月18日Vol.64もよろしくお願いします。
ARI A&S 編集部
【配信】…………………………………………………………………□■□
このメールマガジンは、次のメール配信サービスによって発行
されています。
Melma! : http://www.melma.com/
まぐまぐ: http://www.mag2.com/
Macky!: http://macky.nifty.com/
めろんぱん: http://www.melonpan.net
メルマガ天国:http://melten.com/
E-Magazine: http://www.emaga.com/
カプライト: http://kapu.biglobe.ne.jp/
【配信中止】……………………………………………………………□■□
配信中止をご希望の方がいらっしゃいましたら、お手数ですが、
登録いただいた各配信先で解除いただきますようお願い申し上げ
ます。(みなさまにご登録いただいたメールアドレスは弊社では
記録、収集しておりません)。
Melma! http://www.melma.com/mag/96/m00058796/index_bn.html
まぐまぐ http://www.mag2.com/m/0000086886.htm
Macky! http://macky.nifty.com/cgi-bin/bndisp.cgi?M-ID=poparimm
めろんぱん http://www.melonpan.net/melonpa/mag-detail.php?mag_id=002937
メルマガ天国 http://melten.com/m/10326.html
E-Magazine http://www.emaga.com/info/arimm.html
カプライト http://cgi.kapu.biglobe.ne.jp/m/5842.html
【ご意見・ご感想】……………………………………………………□■□
このメールマガジンが対象としているような技術や音響などの
内容についてご意見、ご感想、投稿など歓迎いたしますので、
なんでもお気軽にお寄せください。
▼ご意見、ご感想送信はこちらのE-Mailアドレスへお願いします。
mailto:news@ari-web.com
□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□ 発行/編集 株式会社エー・アール・アイ
□ Amenity Research Institute Co.,Ltd.
□ 〒192-0081 東京都八王子市横山町6-9 丸多屋ビル8F
□ TEL :0426-56-2771 FAX :0426-56-2654
□ URL : http://www.ari-web.com/
■ お問合せ : mailto:news@ari-web.com
■ Copyright(C) 2004. ARI.CO.,LTD. All Rights Reserved.
□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□■□■□■

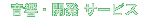 音響・開発サービス
音響・開発サービス Inter BEE 2014 参考出展の報告
Inter BEE 2014 参考出展の報告 エコーキャンセラー ソフトウェア(DSP)
エコーキャンセラー ソフトウェア(DSP) テレビ会議・Web会議を支える音声技術
テレビ会議・Web会議を支える音声技術 PC向けステレオ音源エコーキャンセラー
PC向けステレオ音源エコーキャンセラー 体感振動ユニット在庫放出
体感振動ユニット在庫放出 スピーカーユニット データシート
スピーカーユニット データシート 小型フルレンジスピーカーNS3-193-8A
小型フルレンジスピーカーNS3-193-8A スピーカーユニットの販売、サンプル
スピーカーユニットの販売、サンプル 音響と開発 : 用語 - 音響測定の信号
音響と開発 : 用語 - 音響測定の信号 音響と開発 : 用語 - ディレイ
音響と開発 : 用語 - ディレイ エコーキャンセラー付き音声認識デモ
エコーキャンセラー付き音声認識デモ 高速H∞フィルタによる適応制御
高速H∞フィルタによる適応制御 体感振動システムBassShaker
体感振動システムBassShaker バーチャルサラウンド
バーチャルサラウンド ホワイトノイズ、ピンクノイズ
ホワイトノイズ、ピンクノイズ サウンドコラムと技術開発コラム
サウンドコラムと技術開発コラム 無響室 - 音響測定設備の紹介
無響室 - 音響測定設備の紹介 ノイズキャンセル マイク 製品情報
ノイズキャンセル マイク 製品情報