ダミーヘッドのトラッキング付き音響配信
アメニティ&サウンド 音と快適の空間へ vol.41
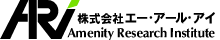
ARI CO.,LTD.
- Home >
- 音響と開発 >
- アメニティ&サウンド >
- バックナンバー >
- vol.41 ダミーヘッドのトラッキング付き音響配信

メールマガジン「アメニティ サウンド 音と快適の空間へ」は、現在、休刊中です。 バックナンバーのコラムの内、サウンドコラムと技術開発コラムは、 サウンド、技術開発コラム に再編集、一部加筆修正して掲載していますので併せてご利用ください。
■□■□■□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
■ アメニティ&サウンド 音と快適の空間へ【Vol.41】2003年11月6日
□ ダミーヘッドのトラッキング付き音響配信
□ http://www.ari-web.com/
□■□□□□□□□□□□□□ 株式会社エー・アール・アイ □■□■
□はじめての方へ、
このメールマガジンのご登録をいただきましてありがとうございます。
「アメニティ&サウンド 音と快適の空間へ」は、隔週(第1、第3木曜日)
にお届けしています。内容を充実できるようにがんばりますので、末永く
お付き合いいただけますようお願い申し上げます。
■□■□■ CONTENTS Vol.41 □□□□□□□□□□□□□□□□□
1.技術と開発の閑話(6)
リアルタイムとベストエフォート (後編)
2.サウンド(39)
ダミーヘッドのトラッキング付き音響配信
3.3GPP音声通信(34)
GSM音響規格 − 送話雑音測定
4.RFIDの採用(URLクリッピング)
………………………………………………………………………………………
■1.技術と開発の閑話(6) リアルタイムとベストエフォート (後篇)
………………………………………………………………………………………
今回はリアルタイム性とベストエフォートに関する話題の後編です。
▼前回までの内容はバックナンバーをご覧ください。
http://www.ari-web.com/mm/bn/index.htm
■ベストエフォートと通信回線に対する要求
ベストエフォート通信でのストリーミングでは、通信が途絶えると、
映像の場合には、コマ落ちのような処理をすることで、連続性を維持
することになりますが、音響の場合には、音が途切れてしまい、映像
ほど許容できる品質で継続再生することができません。
そのためReal Playerなどの可変通信速度に対応したストリーミング
では、通信速度にあわせてできるだけバッファが途絶えないように、
再生の速度や以後の通信量を控えるように変化させて、最後まで音が
継続するような優先になっています(映像が停止して音だけになります)。
映像も画像品質を低下させないほうが好ましいのは確かですが、視覚
より、聴覚の方が敏感で、音の最低品質は、比較的高く保たれないと、
非常に気になります。本来、ベストエフォートのHTTPプロトコルの上
での音の通信は、あまり適していない基盤に築かれてネットワーク利
用している状況です。
当然、ネットワークが最大要求時に通信最低品位を満たされるような
設計にすることはインターネットの規模やスケール変動に適していま
せんので、現在のネットワークプロトコルのまま、最低品質を保証で
きるリアルタイム性のストリーミングは、実現することが難しいこと
は通信事業者でなくても容易に想像できます。
今年の8月のCNETのコラムに、インターネットのベストエフォート
に関するコラムが掲載されていました。
▼「ベストエフォート」が死語となる日
Dr. Lawrence Roberts
CNET Japan エキスパートの視点: 2003年8月29日
http://japan.cnet.com/news/pers/story/0,2000047682,20060642,00.htm
次世代ルータに関連してベストエフォートでは、ブロードバンド型
マルチメディア・ストリーミングが要求する最低通信品質を維持でき
ないことから「死語となる日」の表題となっている、速度バランスを
取る次世代ルータの動向などを話題にしたコラムです。
通信速度の確保が要求されていることはコラムの通りです。...が、
現在、身辺に存在する機器、携帯電話、IP電話、パソコンの動作も、
衛星放送の受信状態なども、ベストエフォートやベストエフォート的
に、最悪の場合サービスが停止することもあるのが前提の機器が多数
です。
さらに、今後、複数回線のベストエフォートを推し進めた4G携帯電話
などに向かうことになります(4Gは異なる通信ネットワークをベスト
エフォートで使いわけて通信をすることが目標とされています)。
ネットワーク負荷が局所集中してもブロードキャスト型の性質があっ
て、一方向性が強いビデオ配信などでは、プロキシーでの分散キャッ
シュによる軽減も可能かもしれませんが、オンラインの対戦ゲームの
場合には、プロキシーが有効に利用できませんので、オンライン対戦
ゲームの通信が局所集中するとサービスが維持できないような限界、
回線破綻する可能性が存在します。
ベストエフォートが死語となったといえるほど安定させるには、新た
な負荷分散や帯域確保の技術、対策、プロトコル上の工夫などが必要
なのだろうと思います。
それでは、次回もよろしくお付き合いください。 (^^)
▼ARIは、デジタル機器のハードウェア、ファームウェアの開発を
お手伝いしています。
http://www.ari-web.com/develop/index.htm
………………………………………………………………………………………
■2.サウンド(39) ダミーヘッドのトラッキング付き音響配信
………………………………………………………………………………………
このコラムは音や音響機器などについての話題をお届けしています。
10月28日にNTTコミュニケーション科学基礎研究所 人間情報研究部
が報道向けに開発中の「テレヘッド」というダミーヘッドを利用した
3D音響の配信装置を報道向けに公開したそうです。
▼コンサート鑑賞は身代わりの人形が
NTT R&Dフォーラム2003 in 厚木
インプレス インターネットWATCH 10月29日
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2003/10/29/941.html
このテレヘッドという装置には、3軸のモーターを装備しヘッドホン
のセンサーに合わせてダミーヘッドが動く、遠隔状態で3D音響の
ヘッド・トラッキングを行うダミーヘッドです。
ヘッド・トラッキングというのは、頭の動きに追従(トラッキング)
して、フィードバックを行うもので、立体音響の場合、音源の位置が
頭の方向にあわせて相対的な関係を移動させることで、その場にいる
ような音場を作ります。
昨年、HTML版のアメニティ&サウンドでもヘッド・トラッキングに
ついて触れていますが、立体音響では、耳の位置差が大きい斜め方向
や左右方向の方向感はうまく行きますが、前方、後方の方向感が弱い
傾向にあります。
ヘッド・トラッキング技術を利用すると、例えば正面に定位する音源
に対しても頭の動きとの相対関係が保たれることによって、定位感が
改善され、全体にリアリティが増した立体音響空間が再現されます。
▼アメニティ&サウンド マンスリー 2002年9月
ヘッドマウントディスプレイと立体音響(前編)
http://www.ari-web.com/mm/html/20020927.htm
ヘッドマウントディスプレイと立体音響(後編)
http://www.ari-web.com/mm/html/20021025.htm
「テレヘッド」は通信ネットワーク経由で使用して身体の不自由な人
がコンサートホールの臨場感を味わえるようにするシステムなどに利
用できると紹介されています。
ヘッド・トラッキングで「テレヘッド」のように実際にダミーヘッド
を動かすというものは珍しいと思います。
開発中の「テレヘッド」では、アナログ回線とセンサーの線という組
み合わせで実装されていましたが、ヘッドホンの代わりにマンスリー
でも話題にしましたヘッドマウントディスプレイを利用して映像も含
めてトラッキングをすると(ダミーヘッドにカメラもつける)、映像と
音がトラッキングされてさらに疑似体験として面白いかもしれません。
「テレヘッド」は、現在のところは、モーターのノイズ音を拾ってし
まうという欠点があるとのことで、モーターの静穏性を改善する必要
があるとされています。
ダミーヘッド部分をロボットで実現されれば、ロボットにしか行けな
いような場所や、遠隔地で立体音響での擬似体験もできます。ロボッ
トにするとヘッドトラッキング意外に、本体の移動も可能ですから、
より似体験的です。この場合には、映像もステレオ・ディスプレイに
して立体視にすると、さらに、面白いですね。
それでは、次回もよろしくお付き合いください。(^^)
前回までの内容はバックナンバーをご覧ください。
▼バックナンバー目次
http://www.ari-web.com/mm/bn/index.htm
………………………………………………………………………………………
■3.3GPP音声通信(34) GSM音響規格 − 送話雑音測定
………………………………………………………………………………………
NTTドコモとKDDIが10月30日に2003年度中間決算を発表しました。
NTTドコモは9月末の時点でFOMA契約社数が100万を突破し、年度末
の契約数の目標を200万に上方修正すると発表しています。一方、
KDDIは営業利益が前年同期比164.8%増のauの依然続く好調ぶりの
アピールとと新サービス「CDMA 1X WIN(ウィン)」による3Gサービス
の優位性の確保を発表しています。
▼NTTドコモ中間決算、FOMAが100万契約を突破し、売上6.4%増
CNET Japan 2003年10月30日
http://japan.cnet.com/news/com/story/0,2000047668,20061716,00.htm
▼KDDIの2003年4月〜9月期連結決算、減収するも純利益は前年
同期の4倍以上
CNET Japan 2003年10月31日
http://japan.cnet.com/news/com/story/0,2000047668,20061731,00.htm
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
前回はGSM音響規格の音響エコー測定についてご紹介しました。今回
は送話雑音測定についてお話しします。
▼前回までの内容はホームページのバックナンバーをご覧ください。
http://www.ari-web.com/mm/
■8.Sending Idle Channel Noise (送話雑音)
送話雑音測定とは、送話方向の測定で端末が通話状態で無信号時の
雑音レベルを評価するための測定です。相手の端末とつながってい
て話をしていない状態で相手に音がどの程度聞こえているかを評価
するということです。
送話時の雑音とは端末からPOI点までの全てのノイズの事を指して
おり、端末のマイクに入力される周囲雑音のノイズや伝送経路のノ
イズなど送話経路の全てのノイズを含みます。
測定にはLRGP(テストヘッド)を使用します。測定環境については
周囲環境が30dBspl(A)以下の環境で測定する様に規定されています。
これらの測定条件は3GPP規格の送話雑音測定と同じです。
▼3GPP規格の送話雑音測定は以前にご紹介しました。
http://www.ari-web.com/mm/bn/20021121.htm
以上の条件を満たした上で端末を通話状態にし、POI出力点での周
波数特性を測定し、全周波帯域の総和レベルを求めます。
この求めた総和レベルが送話雑音レベルということになります。
送話雑音測定は無信号時の雑音レベルを評価するので試験信号は
使用しません。
GSMでは送話雑音はは以下の値で規定されています。
・送話雑音レベル :-64dBm0P以下
(周囲雑音30dBspl(A)以下のにて)
規格値は3GPP規格ののナローバンドと同じ値で、全周波数帯域での
総和レベルです。
…… [dBm0] ………………………………………………………
3GPPやGSM規格ではPOI点に入出力する電圧に対して
[dBm0]という単位が使用されています。これはPOI点
に入力される[dBm]値です。
例えば、POI入力に-16[dBm0]という電圧が規定されて
いる場合、「発振器の信号出力をPOI点で-16[dBm]に
なる様に出力する」という意味です。発振器の出力電圧
とPOI点の入力電圧に増減が無い場合、[dBm0]=[dBm]
として扱う事ができます。
[dBm0]の後ろについている[P]はPsophometer weight-
ingを使用して評価する(ITU-T .41で規定されている
ソホメータ特性をPOI出力点に周波数重み付けして測定
する)という意味です。
………………………………………………………………………
▼[dBm](デシベル単位)は以前にご紹介しました。
http://www.ari-web.com/mm/bn/20030206.htm
送話雑音レベルが大きすぎると相手の声が聞き取りにくくなったり、
雑音の周波数成分によっては相手の声をマスキングするなどど通話
品質に著しく影響するので、送話雑音レベルは十分に抑えられてい
る必要があります。
次回は受話雑音測定についてお届けします。
▼ARIは3GPP,GSM,PDC音響測定に対応した「3G携帯通信開発用
音響測定システム MTA-01WB-S」を開発・販売しています。
http://www.ari-web.com/mobile/3g/mta01-wbs/info-3gpp.htm
▼GSM端末音響システム 製品概要(MTA-01WB-S)
http://www.ari-web.com/mobile/3g/mta01-wbs/info-gsm.htm
………………………………………………………………………………………
■4.RFIDの採用(URLクリッピング)
………………………………………………………………………………………
WEB参照可能な掲載記事などから毎日伝えられるニュースや記事から
気になる情報や、翌日には埋もれてしまいそうな記事をピックアップ
してご紹介しています(このメールマガジンの発行周期が隔週という
こともあって新しい記事ばかりではありません)。
■RFIDの採用
RFID(Radio Frequency Identification)、無線利用の非接触型自動識別
チップの話題は、ベネトンやウォルマート社などの流通管理などでの
採用や延期などで度々目にするようになっていますが、学校でも採用
したところが出たようです。
▼『RFID』を生徒の管理に利用する学校が登場
Hot Wired Japan News 2003年10月24日
http://www.hotwired.co.jp/news/news/culture/story/20031028206.html
何かと、プライバシー問題との関係で、批判の強いRFIDチップの埋め
込みですが、最も典型的に人の行動記録を行う利用方法が普及の初期
段階で採用されるとは思いませんでしたので学校の例は意外です。
記事によると、校長が無線技術の活用に本腰を入れているそうです。
恐らく、ウォルマートのタグも、少し離れた場所では、通信不能な
タイプだと推測しますから、商品タグを各所で無線トラッキングする
ことはできなそうですが...記事では、RFIDチップで今どこにいるか
追跡できるという批判のためもあってか、商品購入取り外すつもりだ
という言明になっています。
▼ウォルマート、RFIDタグは商品販売時点で取り外すと言明
Hot Wired Japan News 2003年3月26日
http://www.hotwired.co.jp/news/news/business/story/20030328103.html
在庫管理などの面からある程度の距離での通信が可能なものを利用す
るのかもしれませんが、RFIDチップの多くは数mmから数cmが交信
可能な距離で、1mと超えるような方式では、電池内臓のIDタグでない
と無理ですから、商品に取り付けられるタグでは、交信距離が短くて
たとえ、交信装置が各所にあったところで、極近傍に頻繁に訪れない
と人がどこにいるのかをトラッキングするのは不可能ではないでしょ
うか(散在的にはトラッキングできるかもしれませんが、それも利用
可能な識別ができてのことですし)。
RFIDは、利用方法に問題がなければ、発展性が期待される技術ですか
ら米国防総省も後押しするようです。
▼米国防総省、全納入業者にICタグ採用を義務付けへ
Hot Wired Japan News 2003年10月27日
http://www.hotwired.co.jp/news/news/business/story/20031028107.html
RFIDの記事では、バーコードのように近づけなくて済むなどの記述が
目立ちますが、長くでも数10センチが限度のものがほとんどですから、
非接触であっても、近づけなくてもすむものは少ないのではないかと
思いますが...
………………………………………………………………………………………
■編集後記
パブジーン(Pubzine)のメール配信サイトが終了することになりまし
た。パブジーンの配信は2月9日でサービス終了となります。
パブジーンでの新規登録は、2003年11月10日12時まで、サイトの閲覧
と配信が、2004年2月9日12時で終了します。
パブジーンでご登録いただいた方にはパブジーンからのサービス終了
の案内が送信されていると思いますが、案内に記載されておりました
ようにサービス移管処理はされませんので、メールアドレス等が他社
に委譲される心配はありません。読者登録されたメールアドレスは、
破棄されます。
パブジーンをご利用の方はご存知のように、登録に手数がかかっても、
読者登録の意思を尊重するダブル・オプトイン方式を取るような信頼
の置けるサイトですからサービス終了は残念です。
もし、継続して受信していただけるようでしたら、パブジーンをご利
用の読者の皆様には、サービス停止後は、他の配信サイトにご登録い
ください。弊社ではご登録いただいたメールアドレスを取得しており
ませんので、お手数をお掛けいたしますが、移行いただく場合には、
ご希望の配信サイトでのご登録をお願いいたします。
なお、パブジーンでの配信は、サービス終了日まで従来通り継続いた
しますので、今後とも宜しくお願い申し上げます。
それでは、次回、2003年11月20日Vol.42もよろしくお願いします。
ARI A&S 編集部
【配信】……………………………………………………………………………
このメールマガジンは、次のメール配信サービスによって発行
されています。
Melma! : http://www.melma.com/
Pubzine: http://www.pubzine.com/
まぐまぐ: http://www.mag2.com/
Macky!: http://macky.nifty.com/
めろんぱん: http://www.melonpan.net
メルマガ天国:http://melten.com/
E-Magazine: http://www.emaga.com/
カプライト: http://kapu.biglobe.ne.jp/
【配信中止】………………………………………………………………………
配信中止をご希望の方がいらっしゃいましたら、お手数ですが、
登録いただいた各配信先で解除いただきますようお願い申し上げ
ます。(みなさまにご登録いただいたメールアドレスは弊社では
記録、収集しておりません)。
Melma! http://www.melma.com/mag/96/m00058796/index_bn.html
Pubzine http://www.pubzine.com/detail.asp?id=17084
まぐまぐ http://www.mag2.com/m/0000086886.htm
Macky! http://macky.nifty.com/cgi-bin/bndisp.cgi?M-ID=poparimm
めろんぱん http://www.melonpan.net/melonpa/mag-detail.php?mag_id=002937
メルマガ天国 http://melten.com/m/10326.html
E-Magazine http://www.emaga.com/info/arimm.html
カプライト http://cgi.kapu.biglobe.ne.jp/m/5842.html
【ご意見・ご感想】………………………………………………………………
なお、このメールマガジンが対象としているような技術や音響
などの内容についてご意見、ご感想、投稿など歓迎いたします
ので、なんでもお気軽にお寄せください。
▼ご意見、ご感想送信はこちらのE-Mailアドレスへお願いします。
mailto:news@ari-web.com
□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□ 発行/編集 株式会社エー・アール・アイ
□ Amenity Research Institute Co.,Ltd.
□ 〒192-0081 東京都八王子市横山町6-9 丸多屋ビル8F
□ TEL :0426-56-2771 FAX :0426-56-2654
□ URL : http://www.ari-web.com/
■ お問合せ : mailto:news@ari-web.com
■ Copyright(C) 2002-2003 ARI.CO.,LTD. All Rights Reserved.
□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□■□■□■
■ アメニティ&サウンド 音と快適の空間へ【Vol.41】2003年11月6日
□ ダミーヘッドのトラッキング付き音響配信
□ http://www.ari-web.com/
□■□□□□□□□□□□□□ 株式会社エー・アール・アイ □■□■
□はじめての方へ、
このメールマガジンのご登録をいただきましてありがとうございます。
「アメニティ&サウンド 音と快適の空間へ」は、隔週(第1、第3木曜日)
にお届けしています。内容を充実できるようにがんばりますので、末永く
お付き合いいただけますようお願い申し上げます。
■□■□■ CONTENTS Vol.41 □□□□□□□□□□□□□□□□□
1.技術と開発の閑話(6)
リアルタイムとベストエフォート (後編)
2.サウンド(39)
ダミーヘッドのトラッキング付き音響配信
3.3GPP音声通信(34)
GSM音響規格 − 送話雑音測定
4.RFIDの採用(URLクリッピング)
………………………………………………………………………………………
■1.技術と開発の閑話(6) リアルタイムとベストエフォート (後篇)
………………………………………………………………………………………
今回はリアルタイム性とベストエフォートに関する話題の後編です。
▼前回までの内容はバックナンバーをご覧ください。
http://www.ari-web.com/mm/bn/index.htm
■ベストエフォートと通信回線に対する要求
ベストエフォート通信でのストリーミングでは、通信が途絶えると、
映像の場合には、コマ落ちのような処理をすることで、連続性を維持
することになりますが、音響の場合には、音が途切れてしまい、映像
ほど許容できる品質で継続再生することができません。
そのためReal Playerなどの可変通信速度に対応したストリーミング
では、通信速度にあわせてできるだけバッファが途絶えないように、
再生の速度や以後の通信量を控えるように変化させて、最後まで音が
継続するような優先になっています(映像が停止して音だけになります)。
映像も画像品質を低下させないほうが好ましいのは確かですが、視覚
より、聴覚の方が敏感で、音の最低品質は、比較的高く保たれないと、
非常に気になります。本来、ベストエフォートのHTTPプロトコルの上
での音の通信は、あまり適していない基盤に築かれてネットワーク利
用している状況です。
当然、ネットワークが最大要求時に通信最低品位を満たされるような
設計にすることはインターネットの規模やスケール変動に適していま
せんので、現在のネットワークプロトコルのまま、最低品質を保証で
きるリアルタイム性のストリーミングは、実現することが難しいこと
は通信事業者でなくても容易に想像できます。
今年の8月のCNETのコラムに、インターネットのベストエフォート
に関するコラムが掲載されていました。
▼「ベストエフォート」が死語となる日
Dr. Lawrence Roberts
CNET Japan エキスパートの視点: 2003年8月29日
http://japan.cnet.com/news/pers/story/0,2000047682,20060642,00.htm
次世代ルータに関連してベストエフォートでは、ブロードバンド型
マルチメディア・ストリーミングが要求する最低通信品質を維持でき
ないことから「死語となる日」の表題となっている、速度バランスを
取る次世代ルータの動向などを話題にしたコラムです。
通信速度の確保が要求されていることはコラムの通りです。...が、
現在、身辺に存在する機器、携帯電話、IP電話、パソコンの動作も、
衛星放送の受信状態なども、ベストエフォートやベストエフォート的
に、最悪の場合サービスが停止することもあるのが前提の機器が多数
です。
さらに、今後、複数回線のベストエフォートを推し進めた4G携帯電話
などに向かうことになります(4Gは異なる通信ネットワークをベスト
エフォートで使いわけて通信をすることが目標とされています)。
ネットワーク負荷が局所集中してもブロードキャスト型の性質があっ
て、一方向性が強いビデオ配信などでは、プロキシーでの分散キャッ
シュによる軽減も可能かもしれませんが、オンラインの対戦ゲームの
場合には、プロキシーが有効に利用できませんので、オンライン対戦
ゲームの通信が局所集中するとサービスが維持できないような限界、
回線破綻する可能性が存在します。
ベストエフォートが死語となったといえるほど安定させるには、新た
な負荷分散や帯域確保の技術、対策、プロトコル上の工夫などが必要
なのだろうと思います。
それでは、次回もよろしくお付き合いください。 (^^)
▼ARIは、デジタル機器のハードウェア、ファームウェアの開発を
お手伝いしています。
http://www.ari-web.com/develop/index.htm
………………………………………………………………………………………
■2.サウンド(39) ダミーヘッドのトラッキング付き音響配信
………………………………………………………………………………………
このコラムは音や音響機器などについての話題をお届けしています。
10月28日にNTTコミュニケーション科学基礎研究所 人間情報研究部
が報道向けに開発中の「テレヘッド」というダミーヘッドを利用した
3D音響の配信装置を報道向けに公開したそうです。
▼コンサート鑑賞は身代わりの人形が
NTT R&Dフォーラム2003 in 厚木
インプレス インターネットWATCH 10月29日
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2003/10/29/941.html
このテレヘッドという装置には、3軸のモーターを装備しヘッドホン
のセンサーに合わせてダミーヘッドが動く、遠隔状態で3D音響の
ヘッド・トラッキングを行うダミーヘッドです。
ヘッド・トラッキングというのは、頭の動きに追従(トラッキング)
して、フィードバックを行うもので、立体音響の場合、音源の位置が
頭の方向にあわせて相対的な関係を移動させることで、その場にいる
ような音場を作ります。
昨年、HTML版のアメニティ&サウンドでもヘッド・トラッキングに
ついて触れていますが、立体音響では、耳の位置差が大きい斜め方向
や左右方向の方向感はうまく行きますが、前方、後方の方向感が弱い
傾向にあります。
ヘッド・トラッキング技術を利用すると、例えば正面に定位する音源
に対しても頭の動きとの相対関係が保たれることによって、定位感が
改善され、全体にリアリティが増した立体音響空間が再現されます。
▼アメニティ&サウンド マンスリー 2002年9月
ヘッドマウントディスプレイと立体音響(前編)
http://www.ari-web.com/mm/html/20020927.htm
ヘッドマウントディスプレイと立体音響(後編)
http://www.ari-web.com/mm/html/20021025.htm
「テレヘッド」は通信ネットワーク経由で使用して身体の不自由な人
がコンサートホールの臨場感を味わえるようにするシステムなどに利
用できると紹介されています。
ヘッド・トラッキングで「テレヘッド」のように実際にダミーヘッド
を動かすというものは珍しいと思います。
開発中の「テレヘッド」では、アナログ回線とセンサーの線という組
み合わせで実装されていましたが、ヘッドホンの代わりにマンスリー
でも話題にしましたヘッドマウントディスプレイを利用して映像も含
めてトラッキングをすると(ダミーヘッドにカメラもつける)、映像と
音がトラッキングされてさらに疑似体験として面白いかもしれません。
「テレヘッド」は、現在のところは、モーターのノイズ音を拾ってし
まうという欠点があるとのことで、モーターの静穏性を改善する必要
があるとされています。
ダミーヘッド部分をロボットで実現されれば、ロボットにしか行けな
いような場所や、遠隔地で立体音響での擬似体験もできます。ロボッ
トにするとヘッドトラッキング意外に、本体の移動も可能ですから、
より似体験的です。この場合には、映像もステレオ・ディスプレイに
して立体視にすると、さらに、面白いですね。
それでは、次回もよろしくお付き合いください。(^^)
前回までの内容はバックナンバーをご覧ください。
▼バックナンバー目次
http://www.ari-web.com/mm/bn/index.htm
………………………………………………………………………………………
■3.3GPP音声通信(34) GSM音響規格 − 送話雑音測定
………………………………………………………………………………………
NTTドコモとKDDIが10月30日に2003年度中間決算を発表しました。
NTTドコモは9月末の時点でFOMA契約社数が100万を突破し、年度末
の契約数の目標を200万に上方修正すると発表しています。一方、
KDDIは営業利益が前年同期比164.8%増のauの依然続く好調ぶりの
アピールとと新サービス「CDMA 1X WIN(ウィン)」による3Gサービス
の優位性の確保を発表しています。
▼NTTドコモ中間決算、FOMAが100万契約を突破し、売上6.4%増
CNET Japan 2003年10月30日
http://japan.cnet.com/news/com/story/0,2000047668,20061716,00.htm
▼KDDIの2003年4月〜9月期連結決算、減収するも純利益は前年
同期の4倍以上
CNET Japan 2003年10月31日
http://japan.cnet.com/news/com/story/0,2000047668,20061731,00.htm
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
前回はGSM音響規格の音響エコー測定についてご紹介しました。今回
は送話雑音測定についてお話しします。
▼前回までの内容はホームページのバックナンバーをご覧ください。
http://www.ari-web.com/mm/
■8.Sending Idle Channel Noise (送話雑音)
送話雑音測定とは、送話方向の測定で端末が通話状態で無信号時の
雑音レベルを評価するための測定です。相手の端末とつながってい
て話をしていない状態で相手に音がどの程度聞こえているかを評価
するということです。
送話時の雑音とは端末からPOI点までの全てのノイズの事を指して
おり、端末のマイクに入力される周囲雑音のノイズや伝送経路のノ
イズなど送話経路の全てのノイズを含みます。
測定にはLRGP(テストヘッド)を使用します。測定環境については
周囲環境が30dBspl(A)以下の環境で測定する様に規定されています。
これらの測定条件は3GPP規格の送話雑音測定と同じです。
▼3GPP規格の送話雑音測定は以前にご紹介しました。
http://www.ari-web.com/mm/bn/20021121.htm
以上の条件を満たした上で端末を通話状態にし、POI出力点での周
波数特性を測定し、全周波帯域の総和レベルを求めます。
この求めた総和レベルが送話雑音レベルということになります。
送話雑音測定は無信号時の雑音レベルを評価するので試験信号は
使用しません。
GSMでは送話雑音はは以下の値で規定されています。
・送話雑音レベル :-64dBm0P以下
(周囲雑音30dBspl(A)以下のにて)
規格値は3GPP規格ののナローバンドと同じ値で、全周波数帯域での
総和レベルです。
…… [dBm0] ………………………………………………………
3GPPやGSM規格ではPOI点に入出力する電圧に対して
[dBm0]という単位が使用されています。これはPOI点
に入力される[dBm]値です。
例えば、POI入力に-16[dBm0]という電圧が規定されて
いる場合、「発振器の信号出力をPOI点で-16[dBm]に
なる様に出力する」という意味です。発振器の出力電圧
とPOI点の入力電圧に増減が無い場合、[dBm0]=[dBm]
として扱う事ができます。
[dBm0]の後ろについている[P]はPsophometer weight-
ingを使用して評価する(ITU-T .41で規定されている
ソホメータ特性をPOI出力点に周波数重み付けして測定
する)という意味です。
………………………………………………………………………
▼[dBm](デシベル単位)は以前にご紹介しました。
http://www.ari-web.com/mm/bn/20030206.htm
送話雑音レベルが大きすぎると相手の声が聞き取りにくくなったり、
雑音の周波数成分によっては相手の声をマスキングするなどど通話
品質に著しく影響するので、送話雑音レベルは十分に抑えられてい
る必要があります。
次回は受話雑音測定についてお届けします。
▼ARIは3GPP,GSM,PDC音響測定に対応した「3G携帯通信開発用
音響測定システム MTA-01WB-S」を開発・販売しています。
http://www.ari-web.com/mobile/3g/mta01-wbs/info-3gpp.htm
▼GSM端末音響システム 製品概要(MTA-01WB-S)
http://www.ari-web.com/mobile/3g/mta01-wbs/info-gsm.htm
………………………………………………………………………………………
■4.RFIDの採用(URLクリッピング)
………………………………………………………………………………………
WEB参照可能な掲載記事などから毎日伝えられるニュースや記事から
気になる情報や、翌日には埋もれてしまいそうな記事をピックアップ
してご紹介しています(このメールマガジンの発行周期が隔週という
こともあって新しい記事ばかりではありません)。
■RFIDの採用
RFID(Radio Frequency Identification)、無線利用の非接触型自動識別
チップの話題は、ベネトンやウォルマート社などの流通管理などでの
採用や延期などで度々目にするようになっていますが、学校でも採用
したところが出たようです。
▼『RFID』を生徒の管理に利用する学校が登場
Hot Wired Japan News 2003年10月24日
http://www.hotwired.co.jp/news/news/culture/story/20031028206.html
何かと、プライバシー問題との関係で、批判の強いRFIDチップの埋め
込みですが、最も典型的に人の行動記録を行う利用方法が普及の初期
段階で採用されるとは思いませんでしたので学校の例は意外です。
記事によると、校長が無線技術の活用に本腰を入れているそうです。
恐らく、ウォルマートのタグも、少し離れた場所では、通信不能な
タイプだと推測しますから、商品タグを各所で無線トラッキングする
ことはできなそうですが...記事では、RFIDチップで今どこにいるか
追跡できるという批判のためもあってか、商品購入取り外すつもりだ
という言明になっています。
▼ウォルマート、RFIDタグは商品販売時点で取り外すと言明
Hot Wired Japan News 2003年3月26日
http://www.hotwired.co.jp/news/news/business/story/20030328103.html
在庫管理などの面からある程度の距離での通信が可能なものを利用す
るのかもしれませんが、RFIDチップの多くは数mmから数cmが交信
可能な距離で、1mと超えるような方式では、電池内臓のIDタグでない
と無理ですから、商品に取り付けられるタグでは、交信距離が短くて
たとえ、交信装置が各所にあったところで、極近傍に頻繁に訪れない
と人がどこにいるのかをトラッキングするのは不可能ではないでしょ
うか(散在的にはトラッキングできるかもしれませんが、それも利用
可能な識別ができてのことですし)。
RFIDは、利用方法に問題がなければ、発展性が期待される技術ですか
ら米国防総省も後押しするようです。
▼米国防総省、全納入業者にICタグ採用を義務付けへ
Hot Wired Japan News 2003年10月27日
http://www.hotwired.co.jp/news/news/business/story/20031028107.html
RFIDの記事では、バーコードのように近づけなくて済むなどの記述が
目立ちますが、長くでも数10センチが限度のものがほとんどですから、
非接触であっても、近づけなくてもすむものは少ないのではないかと
思いますが...
………………………………………………………………………………………
■編集後記
パブジーン(Pubzine)のメール配信サイトが終了することになりまし
た。パブジーンの配信は2月9日でサービス終了となります。
パブジーンでの新規登録は、2003年11月10日12時まで、サイトの閲覧
と配信が、2004年2月9日12時で終了します。
パブジーンでご登録いただいた方にはパブジーンからのサービス終了
の案内が送信されていると思いますが、案内に記載されておりました
ようにサービス移管処理はされませんので、メールアドレス等が他社
に委譲される心配はありません。読者登録されたメールアドレスは、
破棄されます。
パブジーンをご利用の方はご存知のように、登録に手数がかかっても、
読者登録の意思を尊重するダブル・オプトイン方式を取るような信頼
の置けるサイトですからサービス終了は残念です。
もし、継続して受信していただけるようでしたら、パブジーンをご利
用の読者の皆様には、サービス停止後は、他の配信サイトにご登録い
ください。弊社ではご登録いただいたメールアドレスを取得しており
ませんので、お手数をお掛けいたしますが、移行いただく場合には、
ご希望の配信サイトでのご登録をお願いいたします。
なお、パブジーンでの配信は、サービス終了日まで従来通り継続いた
しますので、今後とも宜しくお願い申し上げます。
それでは、次回、2003年11月20日Vol.42もよろしくお願いします。
ARI A&S 編集部
【配信】……………………………………………………………………………
このメールマガジンは、次のメール配信サービスによって発行
されています。
Melma! : http://www.melma.com/
Pubzine: http://www.pubzine.com/
まぐまぐ: http://www.mag2.com/
Macky!: http://macky.nifty.com/
めろんぱん: http://www.melonpan.net
メルマガ天国:http://melten.com/
E-Magazine: http://www.emaga.com/
カプライト: http://kapu.biglobe.ne.jp/
【配信中止】………………………………………………………………………
配信中止をご希望の方がいらっしゃいましたら、お手数ですが、
登録いただいた各配信先で解除いただきますようお願い申し上げ
ます。(みなさまにご登録いただいたメールアドレスは弊社では
記録、収集しておりません)。
Melma! http://www.melma.com/mag/96/m00058796/index_bn.html
Pubzine http://www.pubzine.com/detail.asp?id=17084
まぐまぐ http://www.mag2.com/m/0000086886.htm
Macky! http://macky.nifty.com/cgi-bin/bndisp.cgi?M-ID=poparimm
めろんぱん http://www.melonpan.net/melonpa/mag-detail.php?mag_id=002937
メルマガ天国 http://melten.com/m/10326.html
E-Magazine http://www.emaga.com/info/arimm.html
カプライト http://cgi.kapu.biglobe.ne.jp/m/5842.html
【ご意見・ご感想】………………………………………………………………
なお、このメールマガジンが対象としているような技術や音響
などの内容についてご意見、ご感想、投稿など歓迎いたします
ので、なんでもお気軽にお寄せください。
▼ご意見、ご感想送信はこちらのE-Mailアドレスへお願いします。
mailto:news@ari-web.com
□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□ 発行/編集 株式会社エー・アール・アイ
□ Amenity Research Institute Co.,Ltd.
□ 〒192-0081 東京都八王子市横山町6-9 丸多屋ビル8F
□ TEL :0426-56-2771 FAX :0426-56-2654
□ URL : http://www.ari-web.com/
■ お問合せ : mailto:news@ari-web.com
■ Copyright(C) 2002-2003 ARI.CO.,LTD. All Rights Reserved.
□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□■□■□■

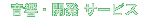 音響・開発サービス
音響・開発サービス Inter BEE 2014 参考出展の報告
Inter BEE 2014 参考出展の報告 エコーキャンセラー ソフトウェア(DSP)
エコーキャンセラー ソフトウェア(DSP) テレビ会議・Web会議を支える音声技術
テレビ会議・Web会議を支える音声技術 PC向けステレオ音源エコーキャンセラー
PC向けステレオ音源エコーキャンセラー 体感振動ユニット在庫放出
体感振動ユニット在庫放出 スピーカーユニット データシート
スピーカーユニット データシート 小型フルレンジスピーカーNS3-193-8A
小型フルレンジスピーカーNS3-193-8A スピーカーユニットの販売、サンプル
スピーカーユニットの販売、サンプル 音響と開発 : 用語 - 音響測定の信号
音響と開発 : 用語 - 音響測定の信号 音響と開発 : 用語 - ディレイ
音響と開発 : 用語 - ディレイ DSP、CPUの開発実績
DSP、CPUの開発実績 エコーキャンセラー付き音声認識デモ
エコーキャンセラー付き音声認識デモ 高速H∞フィルタによる適応制御
高速H∞フィルタによる適応制御 体感振動システムBassShaker
体感振動システムBassShaker バーチャルサラウンド
バーチャルサラウンド ホワイトノイズ、ピンクノイズ
ホワイトノイズ、ピンクノイズ 無響室 - 音響測定設備の紹介
無響室 - 音響測定設備の紹介 ノイズキャンセル マイク 製品情報
ノイズキャンセル マイク 製品情報