海洋の調査
アメニティ&サウンド 音と快適の空間へ vol.48
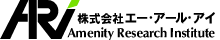
ARI CO.,LTD.
- Home >
- 音響と開発 >
- アメニティ&サウンド >
- バックナンバー >
- vol.48 海洋の調査

メールマガジン「アメニティ サウンド 音と快適の空間へ」は、現在、休刊中です。 バックナンバーのコラムの内、サウンドコラムと技術開発コラムは、 サウンド、技術開発コラム に再編集、一部加筆修正して掲載していますので併せてご利用ください。
■□■□■□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
■ アメニティ&サウンド 音と快適の空間へ【Vol.48】2004年3月4日
□ 海洋の調査
□ http://www.ari-web.com/
□■□□□□□□□□□□□ 株式会社エー・アール・アイ □■□■
□はじめての方へ、
このメールマガジンのご登録をいただきましてありがとうございます。
「アメニティ&サウンド 音と快適の空間へ」は、隔週(第1、第3木曜日)
にお届けしています。内容を充実できるようにがんばりますので、末永く
お付き合いいただけますようお願い申し上げます。
■□■□■ CONTENTS Vol.48 □□□□□□□□□□□□□□□■□
1.技術と開発の閑話(13)
専門ドメインの基礎範囲(2)
2.サウンド(46)
海洋の音響調査 - 前編 -
3.3GPP音声通信(41)
GSM音響規格 − 送話方向 帯域外信号レベル
4.音声読み上げ対応(URLクリッピング)
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1.技術と開発の閑話(13) 専門ドメインの基礎範囲(2)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
前回は、専門領域の基礎をなおざりにしたまま統計ソフトによって高
度な統計手法を利用していることに関するCNET Japanのコラムをきっ
かけに、ソフトウェア開発者の場合「専門とは」「基礎とは」どのよ
うな範囲を指すのかをあらためて考えると、なかなか広範囲で難しい
問題かもしれないというお話をしました。
▼バックナンバー目次
(前回分は現在アップしていませんが近日中に掲載します。もし
すぐに、ご覧になりたい方がいらっしゃいましたら各社配信サー
ビスのバックナンバーでご覧いただけます。)
http://www.ari-web.com/mm/bn/index.htm
専門性、あるいは専門領域というものは、専門の技術分野とそれが利
用される分野の2つの領域についての専門性というものがなければ、
おおよそ、学術的な目的や特殊な問題でなければ成立しないことが多
いかと思います。
ソフトウェアの場合には、OSやコンパイラ、開発ツールなどであれ
ば、ソフトウェアを目的としているためソフトウェアに精通している
ことが、ほぼ全てなりますが、特殊なケースといえ、一般的には、
ソフトウェアの応用を目的とする何かが専門分野となるかと思い
ます。
そのため、ソフトウェアが応用される分野自身についての専門家であ
ることが同時に求められます。
他の職業でも、弁護士であれば、民事なのか刑事なのか、どのような
方面に強いのかというのが専門分野となり、法律や裁判以外の専門分
野の知識にも精通している必要があるでしょう。営業職であれば扱う
商品や業種に関連する知識や理解が必要です。
経済産業省のITスキル・スタンダード(ITSS)の分類は、ソフトウェア
の職種と専門の分類をしますが、11種類の職種と定義されている38の
「専門分野」、そのスキルレベルを定義して評価やIT系の人材育成の
尺度に利用できるようにするもので、ここで述べている専門領域の問
題とは異なります。
ITSSでは、スキルの尺度として、また、スキルパスなどを考える上で
の尺度として、専門分野でのレベルや必要な知識を一般化して定義さ
れていますから、総合力やマネージメント能力などが主な指標として
レベルに採られているといえるかと思います。
▼ITスキルスタンダード
e-Woirds IT用語辞典
(総務省の適したポインティングができると良いのですが、全て
PDFなので、簡単な説明としてe-Wordsをリンクします)
http://e-words.jp/w/ITE382B9E38
2ADE383ABE382B9E382BFE383B3E38380E383BCE38389.html
知識などの項目は、総合的評価尺度として妥当であると納得できるも
のですが、この指標では、特定技術に特化して長けた技術者のスキル
評価はレベルが高くならないかもしれません。当然ではありますが、
スケールをレベル熟成度の基準に取っているため、スケールの小さい
システムを扱う技術者はレベルは低くなると思います(理解が間違っ
ているかもしれません)。
扇風機の制御ソフトの分野で世界的な第一人者がいたとしても、この
尺度においては情報機器などスケールが大きい製品の凡庸な技術者よ
りスキルレベルは低くなるように思います。また、以前良く言われた
少人数精鋭グループでの効率的な開発なども、スケールという点にお
いてレベルが低くなるかもしれません。
それでは、次回もよろしくお付き合いください。(^^)
▼ARIはアプリケーションソフトやデジタル機器の開発などを
お手伝いしています。
http://www.ari-web.com/develop/index.htm
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■2.サウンド(46) 海の音響 - 前編 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
このコラムは音や音響機器などについての話題をお届けしています。
▼海のデータ収集に知恵を絞る海洋学者たち
Hot Wired Japan 2004年2月1日
http://www.hotwired.co.jp/
news/news/technology/story/20040204307.html
アフリカ大陸南岸にセンサーをつけた多数のブイを浮かべてデータ収
集しているディアドリ・バーン教授が海洋科学会議で海洋の情報収集
の発表をしているという紹介記事(具体的な内容には触れられていませ
ん)の中に海の降水量の測定(推定)に雨が海面にあたる音を利用する
方法なども触れられていました。
音響的な手法による降水量推定は、以前から行われていたような気が
しますが、広大な海洋レベルでの学術調査などで音響解析技術が利用
されていることは、一般の認知度は高くないかもしれません。
水中の音響については映画などでおなじみの潜水艦のソナーやイルカ
の超音波探索能力などが一般的に良く知られています。
ソナーのような海洋での音響技術は、タイタニック号が氷山と衝突す
る大事故を起こしたことをきっかけにして開発が開始され、10年以上
後に実現、以後、主に軍事利用するために進歩しました。第二次世界
大戦での潜水艦(Uボート)対ソナーは映画などでも有名で、対Uボート
のために発明されたかのような説明を見かけることもありますが、も
っと前から研究されていたようです。その後も、対ソ潜水艦対策とし
てソナー技術は研究され進歩しています。
音は、空気中よりも水中の方が音速が早く、また、遠くまで伝わりま
す。高音より低音の方が長距離での拡散などによる減衰量が少なく、
長距離での音響探索に適していることから、近年クジラ等海洋生物の
保護問題になっている米軍の低周波ソナー(LFAS : Low Frequency
Active Sonner)が開発されています。
漁船で利用されている魚群探知機も、ソナーですが、一般艦船で利用
されているソナーは、超音波帯域(20KHz以上)や高音域のようです。
魚群探知機で低周波レーダーなどと呼称されているものは、米軍の低
周波(10〜300Hzあたりの帯域)とは異なり、超音波帯域中の低い周波
数と高い周波数の違いを指しているものです。
▼フルノ漁撈航海電子機器をフル装備<船体一括船>!
志摩町「第27源吉丸」竣工。 149トン型・FRPかつお一本釣漁船!
古野電気株式会社
http://www.furuno.co.jp/news/news71.html
このページを見ると、高周波(81KHz)、低周波(24KHz)と紹介されて
おり、超音波帯域が利用されていることが判ります。
ソナーは、大きく分けてアクティブ型とパッシブ型に分けることがで
きます。パッシブ型は集音した音を解析して探索し、アクティブ型は
信号を放射して反射音を解析して探索する方式です。魚群探知機
は、アクティブ型のソナー(レーダー)です。
スクリュー音やエンジン音(モーター音)などを船舶や潜水艦が発して
いる場合には、パッシブ型で解析できますが、対象が静かな場合には
集音しても解析できません(潜水停止している潜水艦など)。対して、
アクティブ型は信号を放射して反射音によって測定するため、対象が
音を発していなくても音を反射する場合には測定することができ
ます。電波の反射を利用する航空レーダーと似た仕組みです。
アクティブ型は、信号を発して、相手にも自分の位置を教えることに
なるため軍事艦船では利用方法が限られます。米軍の低周波ソナーの
技術は、低周波が海中では長距離に伝播することに注目して広範囲の
探索に利用できる技術として研究されたもので、現在のLFASは、200
〜180dBの大出力を放射し遠方の対象物に100dB以上の大音響での反射
音を利用します。当然、艦船搭載するような目的には適していないの
ですが、長距離で利用できるため沿岸から海洋を探索することも可能
です。
クジラなどに対する影響が問題となったのは、100dBを超えるような
大音量をクジラが利用している音の帯域で利用することで、生態にダ
メージを与えるという点です。(クジラはイルカと異なり低音を利用
しているそうです。クジラの唄というのがクジラの利用している音声
帯域ですね)、他の海洋生物にも影響があるかも知れないとされてい
ます。
▼米海軍の低周波ソナーをめぐる訴訟、最終段階へ
Hot Wired Japan 2003年6月30日
http://www.hotwired.co.jp/
news/news/technology/story/20030702306.html
この低周波ソナー(LFAS)が、昨年10月ニュースになっていた沖縄を
はじめ、日本近海で米軍が利用することにしている問題のソナー
です。
110dB以上とも140dBとも言われている大音量を近海の生物にぶつけ
ることになりますし、米国沿岸では禁止した技術ですので海洋研究や
生物保護団体の方などが東アジアでの利用に反対しています。
▼SURTASS LFA (低周波ソナー)
(クジラや亀とフレンドリーイメージの写真が……)
http://www.surtass-lfa-eis.com/
この低周波ソナーの技術自体の応用は、軍事も利用だけではなく近年
の海洋学術調査などに多大な貢献をしているのですが……
つづきは次回に、それでは、次回もよろしくお付き合いください。
(^^)
前回までの内容はバックナンバーをご覧ください。
▼バックナンバー目次
http://www.ari-web.com/mm/bn/index.htm
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■3.3GPP音声通信(41)
GSM音響規格 − 送話方向 帯域外信号レベル
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
2003年度12月の移動電話国内出荷実績が(社)電子情報技術産業協
会JEITAの統計情報で発表されました。移動電話国内出荷数量は前
年度比118.9%と14ヶ月連続のプラスと依然好調となっています。
携帯・自動車電話は11月に比べ上昇し、、4,675千台、前年比120.1
%と15ヶ月連続でプラスとなっており、4ヶ月連続の400万台を越え
ています。公衆PHSは前年比52.6%と先月今月と不振が続いています。
▼統計資料-2003年度移動電話国内出荷実績に掲載されています。
(社)電子情報技術産業協会 JEITA
http://www.jeita.or.jp
□……………………………………………………………………………
■15.Discrimination against out-of-band input signal
(送話方向 帯域外信号レベル)
………………………………………………………………………□■□
前回はGSM音響規格の側音歪 第3次高調波含有率測定でした。今回
は送話方向 帯域外信号レベル測定です。
▼前回までの内容はバックナンバーをご覧ください。
http://www.ari-web.com/mm/
送話方向 帯域外信号レベル測定とは送話時の携帯端末の帯域外の
信号のレベルを評価するための測定です。
ナローバンドであるGSM端末の可聴帯域は4kHzまでで、帯域外の信
号レベルとはそれ以上の周波数の事を指しており、測定ではこの帯
域外の信号が可聴帯域の信号に対し規定のレベル以下であるかを評
価します。
▼ナローバンドとワイドバンドについては以前にご紹介しました。
http://www.ari-web.com/mm/bn/20020704.htm
測定にはLRGP(テストヘッド)を使用し、基準信号には1KHzの正弦
波(Sine Wave)を使用して行います。基準信号に1kHzの周波数を使
用するのは、人間の聴感の感度が高い周波数であるためです。
先ず基準信号(1kHz)を人工口より出力し、MRP点で-4.7dB(Pa)得ら
れる様にレベルを調整します。このMRP点に基準信号を印加した時
のPOI出力点で得られる信号レベルは基準値となります。
次に帯域外の試験信号を人工口より出力し、基準信号同様MRP点で
出力レベルの調整を行い、POI出力点で得られる信号レベルを測定し
ます。
試験信号には4.65kHz,5kHz,6kHz,6.5kHz,7kHz,7.5kHzの正弦波(Sin
e Wave)を使用し、周波数毎に測定を行います。
▼(御参考)3GPP送話測定接続例
http://www.ari-web.com/mobile/3g/mta01-wb/intro_03.htm
基準信号および試験信号の周波数毎のPOI出力点での測定値が得ら
れたら次式により帯域外信号の基準信号とのレベル差を求めます。
【帯域外信号レベルの計算式】
基準信号(1kHz)とのレベル差[dB]
= 20 log (試験信号の出力電圧値 / 基準信号の出力電圧値)
各周波数毎に計算により求めた帯域外信号レベルは、基準信号(1k
Hz)の測定測定値以下で、なおかつ以下のマスクカーブの範囲内で
規格値が規定されています。
Frequency[Hz] limit[dB]
4600 -30
8000 -40
送話方向 帯域外信号レベル測定は3GPPには無い、GSM特有の測定
です。再生帯域の音質を損なわない為に帯域外の信号レベルは十分
に抑制されている必要があります。
次回は受話方向 帯域外信号レベルについてお届します。
▼ARIは3GPP,GSM,PDC音響測定に対応した「3G携帯通信開発用
音響測定システム MTA-01WB-S」を開発・販売しています。
http://www.ari-web.com/mobile/3g/mta01-wbs/info-3gpp.htm
▼GSM端末音響システム 製品概要(MTA-01WB-S)
http://www.ari-web.com/mobile/3g/mta01-wbs/info-gsm.htm
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■4.音声読み上げ対応(URLクリッピング)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
WEB参照可能な掲載記事などから毎日伝えられるニュースや記事から
気になる情報や、翌日には埋もれてしまいそうな記事をピックアップ
してご紹介しています(このメールマガジンの発行周期が隔週という
こともあって新しい記事ばかりではありません)。
■火星探査車の関連
前回の編集後記に、火星探査車の復旧の記事を話題にしましたが、
探査車『オポチュニティー』の調査の結果、火星に水が存在していた
証拠といえるものを発見できたようです。
▼『オポチュニティー』、火星に水が存在した証拠を発見
Hot Wired Japan 2004年3月2日
http://www.hotwired.co.jp/news/news/
technology/story/20040303301.html
この発表は、前日に3/2に重大な発表をするというNASAの予告付きの
発表だったので、予測通りの発表という印象ではありますが、OSの
リブートを繰り返していた探査車をリモート復活させて、重要目的の
ひとつである水の存在可能性の確認のミッションを成功させたのは、
敬意をもって祝福したいと思います。
探査車は、多くの映像データなどを送信してきていますが、探査車
からのデータ送信についても簡単な記事にされていました(話題にして
いるという程度で詳しくはないです)。
▼火星探査車からのデータ送信、その仕組み
Hot Wired Japan 2004年3月2日
http://www.hotwired.co.jp/news/
news/technology/story/20040303302.html
■音声読み上げ対応
Vol.46の音のコラムでVoiceXMLの話題で音声ブラウザや音声合成など
について触れていましたが、IBMの「らくらくウェブ散策」という音声
合成サービスを使って3/1から厚生労働省のサイトは、音声読上げ対応
になったようです。
▼厚生労働省ホームページ
音声読み上げ/文字拡大サービス
http://www.mhlw.go.jp/onsei/index.html
「らくらくウェブ散策」はアクセスビリティの向上の一環として位置
づけられており、デジタルディバイドを解消するためのツールと紹介
されています。
完全ではないのは仕方がないのですが、「デジタルディバイドを解消
する」には、動作条件が……Windows 98〜Windows XPのIE5.5 SP2
以上という条件なので、この時点ですでに超えられない壁が存在して
いるかもしれません。
Vol.46では車載の機器での音声利用についてハンズフリーについて触
れていますが、米General Motorsの車載システムにIBMの音声技術が
(WebSphere)採用されるようです。
▼GMの車載システム子会社、IBMの音声応対ソフトを採用
Yahoo! コンピュータニュース 2004年2月27日
http://headlines.yahoo.co.jp/
hl?a=20040227-00000003-zdn_lp-sci
車載関連の情報機器では、携帯電話のハンズフリー化などと同様に、
事故の原因とさせないために音声技術の採用が多くなってきます。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
■編集後記
技術コラムでITSSを話題に触れていますが、ITSSのスキル熟成度
のレベル設定を見ると「世界を支配しているのはエンジニアでは
なく管理職である。」という言葉が良く理解できるかもしれません。
最近は、何かと「物作り」「技術」「能力、スキル」などと共に、
「無能な管理職」という言葉が出てくる場合があるような気がしま
すが……マネージメントに関わらない職人的技術者は、少なくても
ITSSでは、無能に近いレベルになるかもしれません。
経済的、社会的な活動として、また、一般性のあるスキル評価とし
てはプロジェクトのスケールとマネージメント能力をレベルに採る
のは、何かとプロジェクトマネージャーの能力がクローズアップさ
れている昨今では妥当な基準かと思いますが、知識やスキルパスの
ような側面が強調されると、要領の良いテクニシャンの評価が高く
なる傾向があるので「技術立国」などからは少し遠くなるかもしれ
ません。
外交問題などでマスコミでは「テクニック」が下手だといわれる
日本はテクニシャンであることも重要とはいえます。
それでは、次回、2004年3月18日Vol.49もよろしくお願いします。
ARI A&S 編集部
【配信】…………………………………………………………………□■□
このメールマガジンは、次のメール配信サービスによって発行
されています。
Melma! : http://www.melma.com/
まぐまぐ: http://www.mag2.com/
Macky!: http://macky.nifty.com/
めろんぱん: http://www.melonpan.net
メルマガ天国:http://melten.com/
E-Magazine: http://www.emaga.com/
カプライト: http://kapu.biglobe.ne.jp/
【配信中止】……………………………………………………………□■□
配信中止をご希望の方がいらっしゃいましたら、お手数ですが、
登録いただいた各配信先で解除いただきますようお願い申し上げ
ます。(みなさまにご登録いただいたメールアドレスは弊社では
記録、収集しておりません)。
Melma! http://www.melma.com/mag/96/m00058796/index_bn.html
Pubzine http://www.pubzine.com/detail.asp?id=17084
まぐまぐ http://www.mag2.com/m/0000086886.htm
Macky! http://macky.nifty.com/cgi-bin/bndisp.cgi?M-ID=poparimm
めろんぱん http://www.melonpan.net/melonpa/mag-detail.php?mag_id=002937
メルマガ天国 http://melten.com/m/10326.html
E-Magazine http://www.emaga.com/info/arimm.html
カプライト http://cgi.kapu.biglobe.ne.jp/m/5842.html
【ご意見・ご感想】……………………………………………………□■□
このメールマガジンが対象としているような技術や音響などの
内容についてご意見、ご感想、投稿など歓迎いたしますので、
なんでもお気軽にお寄せください。
▼ご意見、ご感想送信はこちらのE-Mailアドレスへお願いします。
mailto:news@ari-web.com
□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□ 発行/編集 株式会社エー・アール・アイ
□ Amenity Research Institute Co.,Ltd.
□ 〒192-0081 東京都八王子市横山町6-9 丸多屋ビル8F
□ TEL :0426-56-2771 FAX :0426-56-2654
□ URL : http://www.ari-web.com/
■ お問合せ : mailto:news@ari-web.com
■ Copyright(C) 2004. ARI.CO.,LTD. All Rights Reserved.
□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□■□■□■
■ アメニティ&サウンド 音と快適の空間へ【Vol.48】2004年3月4日
□ 海洋の調査
□ http://www.ari-web.com/
□■□□□□□□□□□□□ 株式会社エー・アール・アイ □■□■
□はじめての方へ、
このメールマガジンのご登録をいただきましてありがとうございます。
「アメニティ&サウンド 音と快適の空間へ」は、隔週(第1、第3木曜日)
にお届けしています。内容を充実できるようにがんばりますので、末永く
お付き合いいただけますようお願い申し上げます。
■□■□■ CONTENTS Vol.48 □□□□□□□□□□□□□□□■□
1.技術と開発の閑話(13)
専門ドメインの基礎範囲(2)
2.サウンド(46)
海洋の音響調査 - 前編 -
3.3GPP音声通信(41)
GSM音響規格 − 送話方向 帯域外信号レベル
4.音声読み上げ対応(URLクリッピング)
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1.技術と開発の閑話(13) 専門ドメインの基礎範囲(2)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
前回は、専門領域の基礎をなおざりにしたまま統計ソフトによって高
度な統計手法を利用していることに関するCNET Japanのコラムをきっ
かけに、ソフトウェア開発者の場合「専門とは」「基礎とは」どのよ
うな範囲を指すのかをあらためて考えると、なかなか広範囲で難しい
問題かもしれないというお話をしました。
▼バックナンバー目次
(前回分は現在アップしていませんが近日中に掲載します。もし
すぐに、ご覧になりたい方がいらっしゃいましたら各社配信サー
ビスのバックナンバーでご覧いただけます。)
http://www.ari-web.com/mm/bn/index.htm
専門性、あるいは専門領域というものは、専門の技術分野とそれが利
用される分野の2つの領域についての専門性というものがなければ、
おおよそ、学術的な目的や特殊な問題でなければ成立しないことが多
いかと思います。
ソフトウェアの場合には、OSやコンパイラ、開発ツールなどであれ
ば、ソフトウェアを目的としているためソフトウェアに精通している
ことが、ほぼ全てなりますが、特殊なケースといえ、一般的には、
ソフトウェアの応用を目的とする何かが専門分野となるかと思い
ます。
そのため、ソフトウェアが応用される分野自身についての専門家であ
ることが同時に求められます。
他の職業でも、弁護士であれば、民事なのか刑事なのか、どのような
方面に強いのかというのが専門分野となり、法律や裁判以外の専門分
野の知識にも精通している必要があるでしょう。営業職であれば扱う
商品や業種に関連する知識や理解が必要です。
経済産業省のITスキル・スタンダード(ITSS)の分類は、ソフトウェア
の職種と専門の分類をしますが、11種類の職種と定義されている38の
「専門分野」、そのスキルレベルを定義して評価やIT系の人材育成の
尺度に利用できるようにするもので、ここで述べている専門領域の問
題とは異なります。
ITSSでは、スキルの尺度として、また、スキルパスなどを考える上で
の尺度として、専門分野でのレベルや必要な知識を一般化して定義さ
れていますから、総合力やマネージメント能力などが主な指標として
レベルに採られているといえるかと思います。
▼ITスキルスタンダード
e-Woirds IT用語辞典
(総務省の適したポインティングができると良いのですが、全て
PDFなので、簡単な説明としてe-Wordsをリンクします)
http://e-words.jp/w/ITE382B9E38
2ADE383ABE382B9E382BFE383B3E38380E383BCE38389.html
知識などの項目は、総合的評価尺度として妥当であると納得できるも
のですが、この指標では、特定技術に特化して長けた技術者のスキル
評価はレベルが高くならないかもしれません。当然ではありますが、
スケールをレベル熟成度の基準に取っているため、スケールの小さい
システムを扱う技術者はレベルは低くなると思います(理解が間違っ
ているかもしれません)。
扇風機の制御ソフトの分野で世界的な第一人者がいたとしても、この
尺度においては情報機器などスケールが大きい製品の凡庸な技術者よ
りスキルレベルは低くなるように思います。また、以前良く言われた
少人数精鋭グループでの効率的な開発なども、スケールという点にお
いてレベルが低くなるかもしれません。
それでは、次回もよろしくお付き合いください。(^^)
▼ARIはアプリケーションソフトやデジタル機器の開発などを
お手伝いしています。
http://www.ari-web.com/develop/index.htm
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■2.サウンド(46) 海の音響 - 前編 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
このコラムは音や音響機器などについての話題をお届けしています。
▼海のデータ収集に知恵を絞る海洋学者たち
Hot Wired Japan 2004年2月1日
http://www.hotwired.co.jp/
news/news/technology/story/20040204307.html
アフリカ大陸南岸にセンサーをつけた多数のブイを浮かべてデータ収
集しているディアドリ・バーン教授が海洋科学会議で海洋の情報収集
の発表をしているという紹介記事(具体的な内容には触れられていませ
ん)の中に海の降水量の測定(推定)に雨が海面にあたる音を利用する
方法なども触れられていました。
音響的な手法による降水量推定は、以前から行われていたような気が
しますが、広大な海洋レベルでの学術調査などで音響解析技術が利用
されていることは、一般の認知度は高くないかもしれません。
水中の音響については映画などでおなじみの潜水艦のソナーやイルカ
の超音波探索能力などが一般的に良く知られています。
ソナーのような海洋での音響技術は、タイタニック号が氷山と衝突す
る大事故を起こしたことをきっかけにして開発が開始され、10年以上
後に実現、以後、主に軍事利用するために進歩しました。第二次世界
大戦での潜水艦(Uボート)対ソナーは映画などでも有名で、対Uボート
のために発明されたかのような説明を見かけることもありますが、も
っと前から研究されていたようです。その後も、対ソ潜水艦対策とし
てソナー技術は研究され進歩しています。
音は、空気中よりも水中の方が音速が早く、また、遠くまで伝わりま
す。高音より低音の方が長距離での拡散などによる減衰量が少なく、
長距離での音響探索に適していることから、近年クジラ等海洋生物の
保護問題になっている米軍の低周波ソナー(LFAS : Low Frequency
Active Sonner)が開発されています。
漁船で利用されている魚群探知機も、ソナーですが、一般艦船で利用
されているソナーは、超音波帯域(20KHz以上)や高音域のようです。
魚群探知機で低周波レーダーなどと呼称されているものは、米軍の低
周波(10〜300Hzあたりの帯域)とは異なり、超音波帯域中の低い周波
数と高い周波数の違いを指しているものです。
▼フルノ漁撈航海電子機器をフル装備<船体一括船>!
志摩町「第27源吉丸」竣工。 149トン型・FRPかつお一本釣漁船!
古野電気株式会社
http://www.furuno.co.jp/news/news71.html
このページを見ると、高周波(81KHz)、低周波(24KHz)と紹介されて
おり、超音波帯域が利用されていることが判ります。
ソナーは、大きく分けてアクティブ型とパッシブ型に分けることがで
きます。パッシブ型は集音した音を解析して探索し、アクティブ型は
信号を放射して反射音を解析して探索する方式です。魚群探知機
は、アクティブ型のソナー(レーダー)です。
スクリュー音やエンジン音(モーター音)などを船舶や潜水艦が発して
いる場合には、パッシブ型で解析できますが、対象が静かな場合には
集音しても解析できません(潜水停止している潜水艦など)。対して、
アクティブ型は信号を放射して反射音によって測定するため、対象が
音を発していなくても音を反射する場合には測定することができ
ます。電波の反射を利用する航空レーダーと似た仕組みです。
アクティブ型は、信号を発して、相手にも自分の位置を教えることに
なるため軍事艦船では利用方法が限られます。米軍の低周波ソナーの
技術は、低周波が海中では長距離に伝播することに注目して広範囲の
探索に利用できる技術として研究されたもので、現在のLFASは、200
〜180dBの大出力を放射し遠方の対象物に100dB以上の大音響での反射
音を利用します。当然、艦船搭載するような目的には適していないの
ですが、長距離で利用できるため沿岸から海洋を探索することも可能
です。
クジラなどに対する影響が問題となったのは、100dBを超えるような
大音量をクジラが利用している音の帯域で利用することで、生態にダ
メージを与えるという点です。(クジラはイルカと異なり低音を利用
しているそうです。クジラの唄というのがクジラの利用している音声
帯域ですね)、他の海洋生物にも影響があるかも知れないとされてい
ます。
▼米海軍の低周波ソナーをめぐる訴訟、最終段階へ
Hot Wired Japan 2003年6月30日
http://www.hotwired.co.jp/
news/news/technology/story/20030702306.html
この低周波ソナー(LFAS)が、昨年10月ニュースになっていた沖縄を
はじめ、日本近海で米軍が利用することにしている問題のソナー
です。
110dB以上とも140dBとも言われている大音量を近海の生物にぶつけ
ることになりますし、米国沿岸では禁止した技術ですので海洋研究や
生物保護団体の方などが東アジアでの利用に反対しています。
▼SURTASS LFA (低周波ソナー)
(クジラや亀とフレンドリーイメージの写真が……)
http://www.surtass-lfa-eis.com/
この低周波ソナーの技術自体の応用は、軍事も利用だけではなく近年
の海洋学術調査などに多大な貢献をしているのですが……
つづきは次回に、それでは、次回もよろしくお付き合いください。
(^^)
前回までの内容はバックナンバーをご覧ください。
▼バックナンバー目次
http://www.ari-web.com/mm/bn/index.htm
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■3.3GPP音声通信(41)
GSM音響規格 − 送話方向 帯域外信号レベル
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
2003年度12月の移動電話国内出荷実績が(社)電子情報技術産業協
会JEITAの統計情報で発表されました。移動電話国内出荷数量は前
年度比118.9%と14ヶ月連続のプラスと依然好調となっています。
携帯・自動車電話は11月に比べ上昇し、、4,675千台、前年比120.1
%と15ヶ月連続でプラスとなっており、4ヶ月連続の400万台を越え
ています。公衆PHSは前年比52.6%と先月今月と不振が続いています。
▼統計資料-2003年度移動電話国内出荷実績に掲載されています。
(社)電子情報技術産業協会 JEITA
http://www.jeita.or.jp
□……………………………………………………………………………
■15.Discrimination against out-of-band input signal
(送話方向 帯域外信号レベル)
………………………………………………………………………□■□
前回はGSM音響規格の側音歪 第3次高調波含有率測定でした。今回
は送話方向 帯域外信号レベル測定です。
▼前回までの内容はバックナンバーをご覧ください。
http://www.ari-web.com/mm/
送話方向 帯域外信号レベル測定とは送話時の携帯端末の帯域外の
信号のレベルを評価するための測定です。
ナローバンドであるGSM端末の可聴帯域は4kHzまでで、帯域外の信
号レベルとはそれ以上の周波数の事を指しており、測定ではこの帯
域外の信号が可聴帯域の信号に対し規定のレベル以下であるかを評
価します。
▼ナローバンドとワイドバンドについては以前にご紹介しました。
http://www.ari-web.com/mm/bn/20020704.htm
測定にはLRGP(テストヘッド)を使用し、基準信号には1KHzの正弦
波(Sine Wave)を使用して行います。基準信号に1kHzの周波数を使
用するのは、人間の聴感の感度が高い周波数であるためです。
先ず基準信号(1kHz)を人工口より出力し、MRP点で-4.7dB(Pa)得ら
れる様にレベルを調整します。このMRP点に基準信号を印加した時
のPOI出力点で得られる信号レベルは基準値となります。
次に帯域外の試験信号を人工口より出力し、基準信号同様MRP点で
出力レベルの調整を行い、POI出力点で得られる信号レベルを測定し
ます。
試験信号には4.65kHz,5kHz,6kHz,6.5kHz,7kHz,7.5kHzの正弦波(Sin
e Wave)を使用し、周波数毎に測定を行います。
▼(御参考)3GPP送話測定接続例
http://www.ari-web.com/mobile/3g/mta01-wb/intro_03.htm
基準信号および試験信号の周波数毎のPOI出力点での測定値が得ら
れたら次式により帯域外信号の基準信号とのレベル差を求めます。
【帯域外信号レベルの計算式】
基準信号(1kHz)とのレベル差[dB]
= 20 log (試験信号の出力電圧値 / 基準信号の出力電圧値)
各周波数毎に計算により求めた帯域外信号レベルは、基準信号(1k
Hz)の測定測定値以下で、なおかつ以下のマスクカーブの範囲内で
規格値が規定されています。
Frequency[Hz] limit[dB]
4600 -30
8000 -40
送話方向 帯域外信号レベル測定は3GPPには無い、GSM特有の測定
です。再生帯域の音質を損なわない為に帯域外の信号レベルは十分
に抑制されている必要があります。
次回は受話方向 帯域外信号レベルについてお届します。
▼ARIは3GPP,GSM,PDC音響測定に対応した「3G携帯通信開発用
音響測定システム MTA-01WB-S」を開発・販売しています。
http://www.ari-web.com/mobile/3g/mta01-wbs/info-3gpp.htm
▼GSM端末音響システム 製品概要(MTA-01WB-S)
http://www.ari-web.com/mobile/3g/mta01-wbs/info-gsm.htm
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■4.音声読み上げ対応(URLクリッピング)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
WEB参照可能な掲載記事などから毎日伝えられるニュースや記事から
気になる情報や、翌日には埋もれてしまいそうな記事をピックアップ
してご紹介しています(このメールマガジンの発行周期が隔週という
こともあって新しい記事ばかりではありません)。
■火星探査車の関連
前回の編集後記に、火星探査車の復旧の記事を話題にしましたが、
探査車『オポチュニティー』の調査の結果、火星に水が存在していた
証拠といえるものを発見できたようです。
▼『オポチュニティー』、火星に水が存在した証拠を発見
Hot Wired Japan 2004年3月2日
http://www.hotwired.co.jp/news/news/
technology/story/20040303301.html
この発表は、前日に3/2に重大な発表をするというNASAの予告付きの
発表だったので、予測通りの発表という印象ではありますが、OSの
リブートを繰り返していた探査車をリモート復活させて、重要目的の
ひとつである水の存在可能性の確認のミッションを成功させたのは、
敬意をもって祝福したいと思います。
探査車は、多くの映像データなどを送信してきていますが、探査車
からのデータ送信についても簡単な記事にされていました(話題にして
いるという程度で詳しくはないです)。
▼火星探査車からのデータ送信、その仕組み
Hot Wired Japan 2004年3月2日
http://www.hotwired.co.jp/news/
news/technology/story/20040303302.html
■音声読み上げ対応
Vol.46の音のコラムでVoiceXMLの話題で音声ブラウザや音声合成など
について触れていましたが、IBMの「らくらくウェブ散策」という音声
合成サービスを使って3/1から厚生労働省のサイトは、音声読上げ対応
になったようです。
▼厚生労働省ホームページ
音声読み上げ/文字拡大サービス
http://www.mhlw.go.jp/onsei/index.html
「らくらくウェブ散策」はアクセスビリティの向上の一環として位置
づけられており、デジタルディバイドを解消するためのツールと紹介
されています。
完全ではないのは仕方がないのですが、「デジタルディバイドを解消
する」には、動作条件が……Windows 98〜Windows XPのIE5.5 SP2
以上という条件なので、この時点ですでに超えられない壁が存在して
いるかもしれません。
Vol.46では車載の機器での音声利用についてハンズフリーについて触
れていますが、米General Motorsの車載システムにIBMの音声技術が
(WebSphere)採用されるようです。
▼GMの車載システム子会社、IBMの音声応対ソフトを採用
Yahoo! コンピュータニュース 2004年2月27日
http://headlines.yahoo.co.jp/
hl?a=20040227-00000003-zdn_lp-sci
車載関連の情報機器では、携帯電話のハンズフリー化などと同様に、
事故の原因とさせないために音声技術の採用が多くなってきます。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■
■編集後記
技術コラムでITSSを話題に触れていますが、ITSSのスキル熟成度
のレベル設定を見ると「世界を支配しているのはエンジニアでは
なく管理職である。」という言葉が良く理解できるかもしれません。
最近は、何かと「物作り」「技術」「能力、スキル」などと共に、
「無能な管理職」という言葉が出てくる場合があるような気がしま
すが……マネージメントに関わらない職人的技術者は、少なくても
ITSSでは、無能に近いレベルになるかもしれません。
経済的、社会的な活動として、また、一般性のあるスキル評価とし
てはプロジェクトのスケールとマネージメント能力をレベルに採る
のは、何かとプロジェクトマネージャーの能力がクローズアップさ
れている昨今では妥当な基準かと思いますが、知識やスキルパスの
ような側面が強調されると、要領の良いテクニシャンの評価が高く
なる傾向があるので「技術立国」などからは少し遠くなるかもしれ
ません。
外交問題などでマスコミでは「テクニック」が下手だといわれる
日本はテクニシャンであることも重要とはいえます。
それでは、次回、2004年3月18日Vol.49もよろしくお願いします。
ARI A&S 編集部
【配信】…………………………………………………………………□■□
このメールマガジンは、次のメール配信サービスによって発行
されています。
Melma! : http://www.melma.com/
まぐまぐ: http://www.mag2.com/
Macky!: http://macky.nifty.com/
めろんぱん: http://www.melonpan.net
メルマガ天国:http://melten.com/
E-Magazine: http://www.emaga.com/
カプライト: http://kapu.biglobe.ne.jp/
【配信中止】……………………………………………………………□■□
配信中止をご希望の方がいらっしゃいましたら、お手数ですが、
登録いただいた各配信先で解除いただきますようお願い申し上げ
ます。(みなさまにご登録いただいたメールアドレスは弊社では
記録、収集しておりません)。
Melma! http://www.melma.com/mag/96/m00058796/index_bn.html
Pubzine http://www.pubzine.com/detail.asp?id=17084
まぐまぐ http://www.mag2.com/m/0000086886.htm
Macky! http://macky.nifty.com/cgi-bin/bndisp.cgi?M-ID=poparimm
めろんぱん http://www.melonpan.net/melonpa/mag-detail.php?mag_id=002937
メルマガ天国 http://melten.com/m/10326.html
E-Magazine http://www.emaga.com/info/arimm.html
カプライト http://cgi.kapu.biglobe.ne.jp/m/5842.html
【ご意見・ご感想】……………………………………………………□■□
このメールマガジンが対象としているような技術や音響などの
内容についてご意見、ご感想、投稿など歓迎いたしますので、
なんでもお気軽にお寄せください。
▼ご意見、ご感想送信はこちらのE-Mailアドレスへお願いします。
mailto:news@ari-web.com
□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□ 発行/編集 株式会社エー・アール・アイ
□ Amenity Research Institute Co.,Ltd.
□ 〒192-0081 東京都八王子市横山町6-9 丸多屋ビル8F
□ TEL :0426-56-2771 FAX :0426-56-2654
□ URL : http://www.ari-web.com/
■ お問合せ : mailto:news@ari-web.com
■ Copyright(C) 2004. ARI.CO.,LTD. All Rights Reserved.
□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□■□■□■

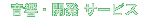 音響・開発サービス
音響・開発サービス エコーサプレッサー / NLP
エコーサプレッサー / NLP Inter BEE 2014 参考出展の報告
Inter BEE 2014 参考出展の報告 エコーキャンセラー ソフトウェア(DSP)
エコーキャンセラー ソフトウェア(DSP) テレビ会議・Web会議を支える音声技術
テレビ会議・Web会議を支える音声技術 AESジャパンコンファレンスin仙台
AESジャパンコンファレンスin仙台 インターネットTV電話の高音質化を実現
インターネットTV電話の高音質化を実現 体感振動ユニット在庫放出
体感振動ユニット在庫放出 スピーカーユニット データシート
スピーカーユニット データシート 小型フルレンジスピーカーNS3-193-8A
小型フルレンジスピーカーNS3-193-8A スピーカーユニットの販売、サンプル
スピーカーユニットの販売、サンプル 残響、残響時間(RT60) : 用語/補足
残響、残響時間(RT60) : 用語/補足 音響と開発 : 用語 - 音響測定の信号
音響と開発 : 用語 - 音響測定の信号 DSP、CPUの開発実績
DSP、CPUの開発実績 ハードウェアと制御システム
ハードウェアと制御システム エコーキャンセラー付き音声認識デモ
エコーキャンセラー付き音声認識デモ 体感振動システムBassShaker
体感振動システムBassShaker バーチャルサラウンド
バーチャルサラウンド ホワイトノイズ、ピンクノイズ
ホワイトノイズ、ピンクノイズ 無響室 - 音響測定設備の紹介
無響室 - 音響測定設備の紹介